決済大手のマスターカードは、アメリカの証券取引委員会(SEC)に提出した年間報告書の中で、ブロックチェーンや仮想通貨に関する取り組みについて発表しました。
SEC(米証券取引委員会)は、アメリカの金融市場を監視する機関です。
企業が投資家に正しい情報を伝えるようにチェックし、不正行為を防ぐ役割を持っています。
マスターカードによると、同社の決済の約30%がデジタルトークンによる取引になっているとのことです。
デジタルトークンとは、インターネット上で使えるお金のようなもので、ブロックチェーン技術を使って安全に取引できます。
仮想通貨(ビットコインやイーサリアムなど)もデジタルトークンの一種です。
仮想通貨をカードで使える!マスターカードの新しい取り組み

マスターカードは、新しいブロックチェーンベースのビジネスモデルを構築しています。
これは、ブロックチェーン技術を活用して、より安全で便利な決済を実現するための取り組みです。
具体的には、「Mastercard Multi-Token Network™(マスターカード・マルチトークンネットワーク)」を使って、金融機関と提携し、プログラム可能な決済を実現しています。
プログラム可能な決済とは?
特定の条件を満たしたときに、自動的にお金を送る仕組みのことです。
たとえば、「商品が届いたら支払いが完了する」といった設定ができます。
これにより、不正取引を防ぐことができます。
このネットワークは2023年にスタートし、次のような機能を提供しています。
✔ ブロックチェーンを使った安全な取引
✔ 異なるブロックチェーン同士のスムーズなやり取り(相互運用性)
✔ 信頼できる取引を行うための共通ルール
これにより、ブロックチェーンを活用した新しい決済サービスがどんどん発展していくと考えられます。
マスターカードは、仮想通貨をもっと身近に使えるようにするため、さまざまな企業と協力しています。
これにより、仮想通貨をカードで簡単に使える仕組みが広がっています。
たとえば、マスターカード対応のカードを使えば、仮想通貨を利用してお買い物ができるようになります。
従来は仮想通貨を現金に換えて使う必要がありましたが、これからはその手間が省けるようになりそうです。
「MetaMaskカード」が登場!仮想通貨ウォレットと連携
最近、マスターカードは**仮想通貨ウォレット「MetaMask(メタマスク)」と提携し、2024年12月に「MetaMaskカード」のパイロット版(試験運用版)を発表しました。
仮想通貨ウォレットは、仮想通貨を保管・送受信するためのデジタルなお財布です。
銀行口座のようなもので、インターネット上で安全に仮想通貨を管理できます。
このカードを使うと、仮想通貨を直接マスターカード加盟店で支払えるようになります。つまり、仮想通貨を普通のお金と同じように買い物に使えるようになるのです。
仮想通貨決済の未来—小売業での普及は進むのか?

マスターカードが仮想通貨決済に本格参入したことで、今後、小売業界や実店舗での仮想通貨の普及が進むのかに注目が集まっています。
現在、仮想通貨の決済は主にオンラインで利用されていますが、オフラインの実店舗でも導入の動きが見られ始めています。
では、世界の事例を見ながら、今後の展望を考えてみましょう。
仮想通貨が実店舗(オフライン)で使われている事例
実店舗で仮想通貨決済を導入する動きはすでに始まっています。以下は代表的な事例です。
✔ エルサルバドルの全国展開
エルサルバドルは2021年にビットコインを法定通貨として採用しました。これにより、スターバックスやマクドナルドなどの大手チェーンを含め、多くの店舗でビットコイン決済が可能になりました。専用のウォレットアプリ「Chivo」を利用すれば、QRコードをスキャンするだけで支払いが完了します。
✔ スイスのルガーノ市
スイスのルガーノ市では、ビットコインやUSDT(テザー)での決済を推奨し、市内のレストランやホテルで仮想通貨が使えるようになっています。税金の支払いも仮想通貨で可能となっており、実生活での活用が広がっています。
✔ 日本国内の取り組み
日本では、秋葉原の一部店舗やビットコインを使った飲食店が登場しています。例えば、ビットコイン決済対応のカフェやバーがあり、暗号資産に興味を持つ人が集まる場所となっています。ただし、法規制や税制の影響で普及は限定的です。
オンラインでの仮想通貨決済の普及事例
オンライン決済の世界では、仮想通貨がすでに幅広く使われています。
✔ ECサイトでの仮想通貨決済
海外では、Shopify(ショッピファイ)やOverstock(オーバーストック)といった大手ECサイトが仮想通貨決済を導入しています。Shopifyではビットコインやイーサリアムを使って商品を購入することができます。
✔ NFTマーケットプレイス
NFT(非代替性トークン)の売買が行われるOpenSea(オープンシー)などのマーケットでは、仮想通貨が主要な決済手段となっています。
✔ 航空券や旅行予約
仮想通貨決済を受け入れている航空会社もあります。例えば、Travala(トラバラ)という旅行予約サイトでは、ビットコインやイーサリアムを使ってホテルや航空券の購入が可能です。
今後、小売業で仮想通貨決済は普及するのか?
仮想通貨が実店舗で広く使われるためには、いくつかの課題があります。
- 価格の変動リスク
仮想通貨は価格変動が大きいため、店舗側がすぐに法定通貨に換金できる仕組みが必要です。マスターカードが提供する「MetaMaskカード」のようなサービスが増えれば、店舗の負担は軽減されるでしょう。 - 規制と税制
国によっては仮想通貨の税制が厳しく、普及のハードルになっています。日本でも、税制の見直しが進めば普及が加速する可能性があります。 - ユーザーの利便性
現在の仮想通貨決済は、ウォレットの管理や送金の手続きが必要で、クレジットカードよりも手間がかかることが課題です。マスターカードのような決済大手が関与することで、よりスムーズな体験が提供されると期待されています。
マスターカードの影響と仮想通貨決済の未来
マスターカードのようなグローバル企業が仮想通貨決済に対応することで、仮想通貨の利用がより簡単になり、実店舗でも普及が進む可能性があります。
特に、既存の決済インフラと統合されることで、消費者にとってのハードルが下がるでしょう。
今後、規制の明確化や安定したステーブルコイン(価格が安定した仮想通貨)の普及が進めば、小売業界でも仮想通貨決済がより一般的になると考えられます。
マスターカードの動きがその鍵を握るかもしれません。
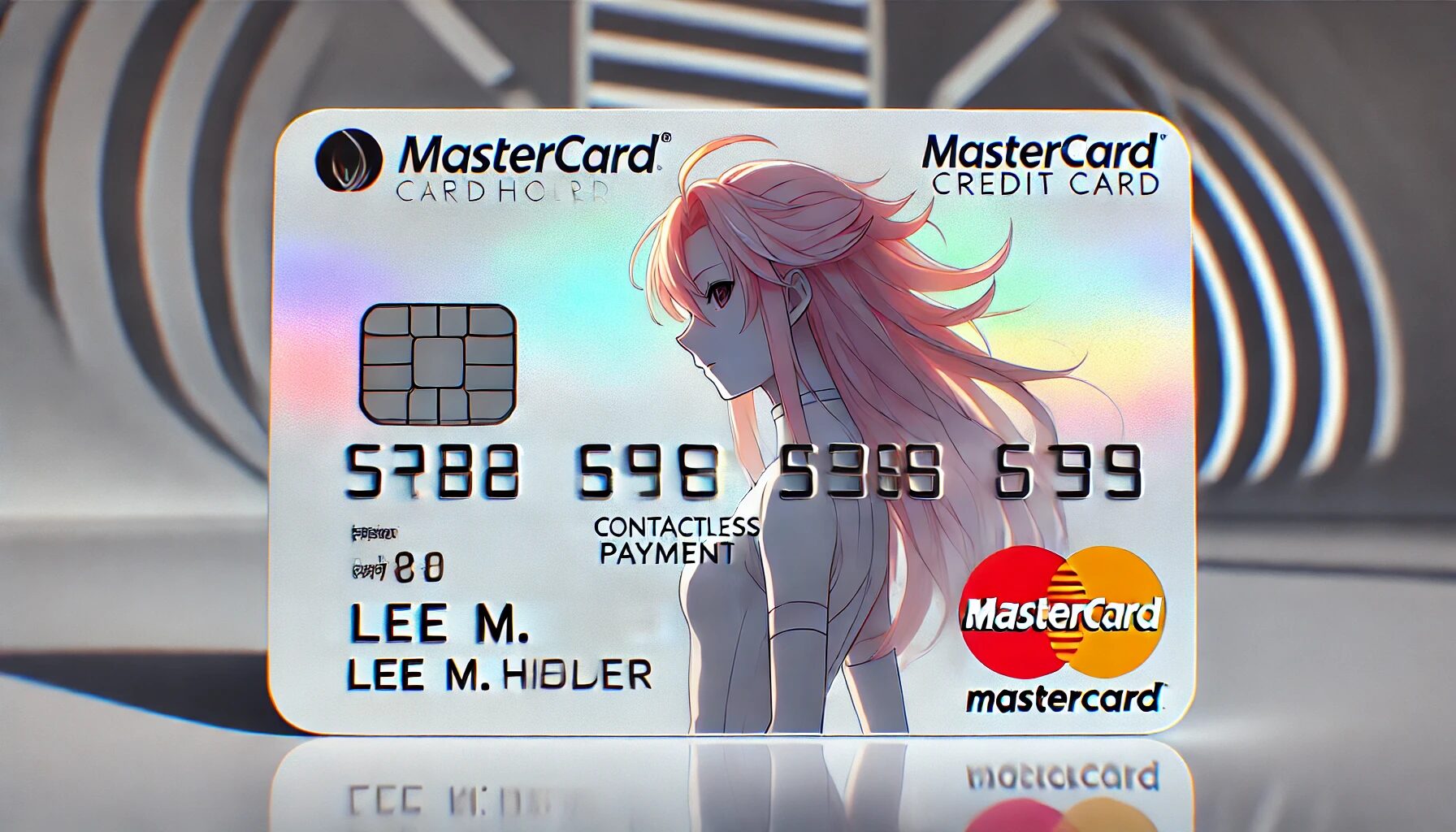








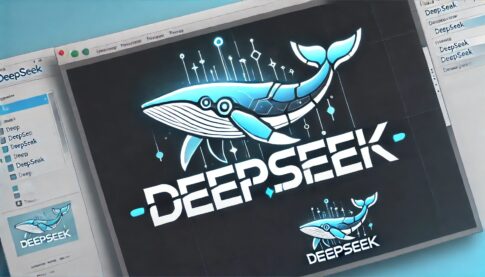



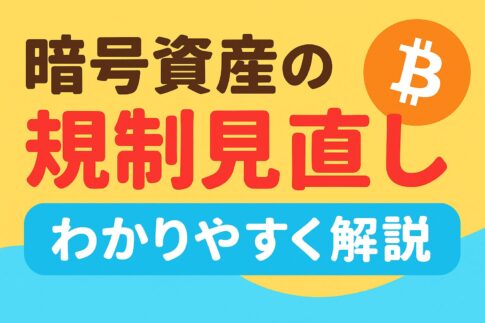




コメントを残す