最近、暗号資産(仮想通貨)に関するルールが変わるかもしれないというニュースが話題になっています。
日本の金融庁が、2025年6月末までに暗号資産の制度を見直す方針を発表しました。これは、加藤勝信財務大臣が国会で説明したものです。
暗号資産は、インターネット上でやり取りできるデジタルなお金のようなもので、ビットコインやイーサリアムが代表的です。
現在、日本では暗号資産を「決済手段」(買い物などの支払いに使うもの)として定義していますが、実際には多くの人が投資目的で売買しています。
そのため、ルールと現実の使い方が合っていないという問題が指摘されています。
また、暗号資産の売買で得た利益は「雑所得」として扱われ、最大で55%(住民税を含む)もの税金がかかる仕組みになっています。
一方で、株などの金融商品は「申告分離課税」として一律20%の税率が適用されており、暗号資産の税制が不公平ではないかという議論もあります。
今回の見直しでは、こうした税制の違いや、暗号資産の法的な位置づけについて広く意見を聞きながら、新しいルールを検討する予定です。
石破茂首相も「Web3(ウェブスリー)の発展はとても重要だ」と述べており、暗号資産がより使いやすくなる可能性があります。
これからどんなルールが決まるのか、今後の動きに注目が集まりそうですね
金融庁がルールを見直しへ
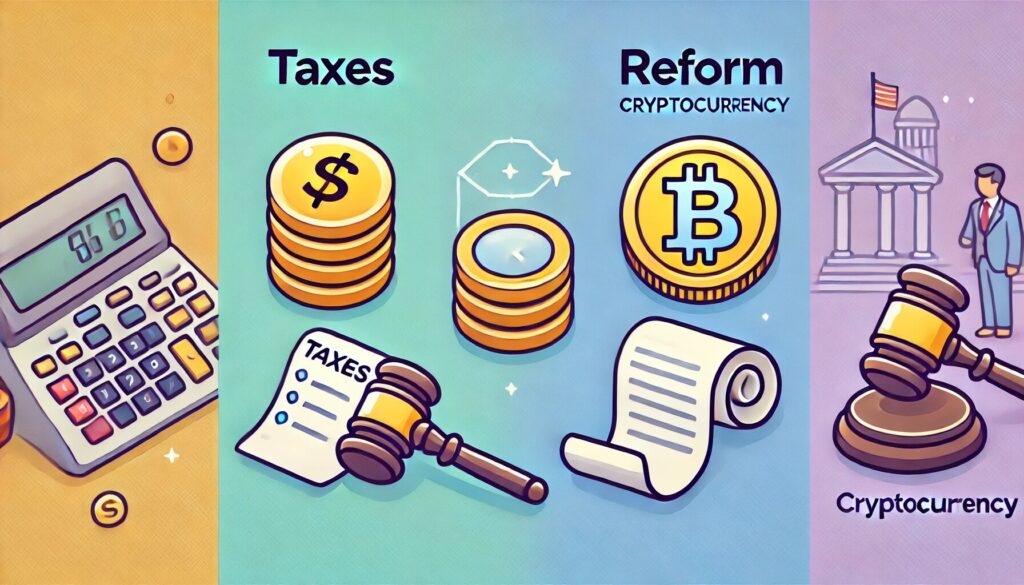
金融庁(きんゆうちょう)は、日本の金融に関するルールを決めたり監督したりする機関です。
内閣府(国の政策を決める役所のひとつ)の外局ですが、財務大臣の指示を受ける立場にあります。
最近、一部の報道によると、金融庁は「資金決済法」(お金のやり取りに関する法律)を改正し、暗号資産(仮想通貨)を「金融商品取引法」の対象とすることを検討しているそうです。
金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)は、株や投資信託などの金融商品を扱うルールを決めた法律です。
もし暗号資産がこの法律の対象になると、取引のルールが変わり、より厳しい規制がかかる可能性があります。
自民党がWeb3に力を入れている
自民党(じみんとう)は、日本の与党(政権を担当している政党)です。
この自民党が2023年12月に「Web3ワーキンググループ」というチームを作りました。
Web3(ウェブスリー)とは、ブロックチェーン技術を使った新しいインターネットの形のことです。
例えば、Web3を活用した代表的なサービスには、次のようなものがあります。
- NFT(非代替性トークン):ゲームのアイテムやデジタルアートを証明する技術で、一度買ったアイテムがずっと自分のものとして記録される。
- 分散型金融(DeFi):銀行を通さずにお金をやり取りする仕組み。例えば、暗号資産を使って個人間でお金を貸し借りできる。
- DAO(分散型自律組織):ブロックチェーン上で運営される会社のようなもの。メンバーが平等に意思決定できる仕組み。
自民党は、2024年4月に発表した「Web3ホワイトペーパー2024」で、個人の暗号資産取引に「申告分離課税」(利益に対して一定の税率をかける方式)を導入することを提言しました。
これが実現すれば、暗号資産の利益に対する税負担が軽くなり、日本でもWeb3分野が発展しやすくなる可能性があります。
暗号資産の税金はなぜ問題なのか?
現在、日本では暗号資産を売買して得た利益(キャピタルゲイン)は、「雑所得(ざつしょとく)」として計算され、給与所得などと合算される「総合課税(そうごうかぜい)」の対象になります。そのため、最大で55%(住民税を含む)もの税金がかかることがあります。
一方、株やFX(外国為替証拠金取引)などの金融商品は「申告分離課税」となっており、税率は一律20%です。つまり、暗号資産だけが特別に高い税率で課税されているのです。
このため、多くの投資家やWeb3のスタートアップ企業が海外に移転してしまう問題が起きています。
なぜ税制見直しが必要なのか?
過去3年ほど、日本の暗号資産税制は少しずつ改善されてきました。
例えば、企業が自社で発行したトークン(暗号資産)にかかる税金が見直され、企業がWeb3事業をしやすくなっています。
しかし、まだ大きな問題が残っています。それが、暗号資産の売買で得た利益に対する税金の高さです。
もし、税率が高すぎるままだと、将来有望な投資家やエンジニアが日本からいなくなってしまい、日本のWeb3業界全体が発展しにくくなる可能性があります。
そのため、税金のルールを世界標準に近づけ、日本国内でもWeb3が成長できる環境を整える必要があるのです。
日本以外の国では暗号資産にどんな税金がかかるの?

暗号資産(仮想通貨)を持っている人や投資を考えている人にとって、税金のルールはとても重要です。
日本では、暗号資産の売買で得た利益に最大55%もの税金がかかることがあります。
でも、世界のほかの国ではどのような税制度になっているのでしょうか?
実は、日本と比べると、税率が低い国や、より投資しやすい制度を作っている国が多く存在します。
主要国の暗号資産の税率を比較
以下は、日本と海外の暗号資産に対する税制の違いをまとめた表です。
| 国 | 税率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日本 | 最大55% | 総合課税(ざっしょとく):給与所得などと合算され、高い税率になる |
| 米国 | 最大20% | キャピタルゲイン課税(売却益に対する課税)、1年以上保有すると優遇 |
| 英国 | 20% | 売却益に対して固定税率を適用 |
| フランス | 30% | 売却益に対して固定税率、暗号資産同士の交換は非課税 |
| UAE(アラブ首長国連邦) | 0% | 個人投資家には課税なし |
この表からわかるように、日本の暗号資産税率は世界的に見ても非常に高いです。
特に、アラブ首長国連邦(UAE)では、暗号資産取引による利益に対する税金がゼロになっています。
日本ではWeb3企業が増えてきていますが、暗号資産に対する税金が高いため、多くのスタートアップ企業が海外に移転してしまう問題があります。
UAEでは税金がかからないため、日本のWeb3企業が拠点を移すケースも増えています。
暗号資産の売買と税金の違い
税金のルールは、暗号資産を売ったときだけではなく、暗号資産同士を交換するときにも関係してきます。
たとえば、日本では「ビットコインをイーサリアムに交換する」といった取引にも税金がかかります。
しかし、フランスでは、こうした「暗号資産同士の交換」は非課税となっています。
これは、フランス政府が暗号資産の取引を活発にするために設けたルールです。
また、米国や英国、ドイツなどでは、日本と同じように暗号資産同士の交換も課税対象になっています。
ですが、日本のように最大55%の高い税率ではなく、一律20%程度のキャピタルゲイン課税が適用される国が多いです。
損失が出たときの扱いも違う
暗号資産を売買して利益が出ることもありますが、逆に損失が出ることもあります。
世界の多くの国では、「損失繰越制度(そんしつくりこしせいど)」があり、損をした場合、翌年以降の利益と相殺(そうさい)して税金を軽減することができます。
しかし、日本にはこの制度がまだ導入されていません。
つまり、日本ではある年に大きな損を出したとしても、翌年の利益と相殺できないため、税金が高くなりやすいのです。
この制度の違いも、日本の暗号資産市場にとって不利な要因になっています。
今後の見通し
金融庁は、2025年6月末までに暗号資産のルールを見直す予定です。
石破茂首相も「Web3の発展は重要」と発言しており、国をあげてWeb3を支援する姿勢を示しています。
今後、税制の変更や新しいルールの導入が進む可能性があり、暗号資産に興味がある人にとっては大きな注目ポイントとなりそうです
特に注目されているのは、次の2点です。
- 申告分離課税の導入(暗号資産の売却益に対して、一律20%の税率を適用する)
- 損失繰越制度の導入(暗号資産取引で出た損失を翌年以降の利益と相殺できるようにする)
これが実現すれば、日本の暗号資産市場はより活発になり、Web3の分野でも世界と戦える環境が整うかもしれません。
今後の動きに注目していきましょう。
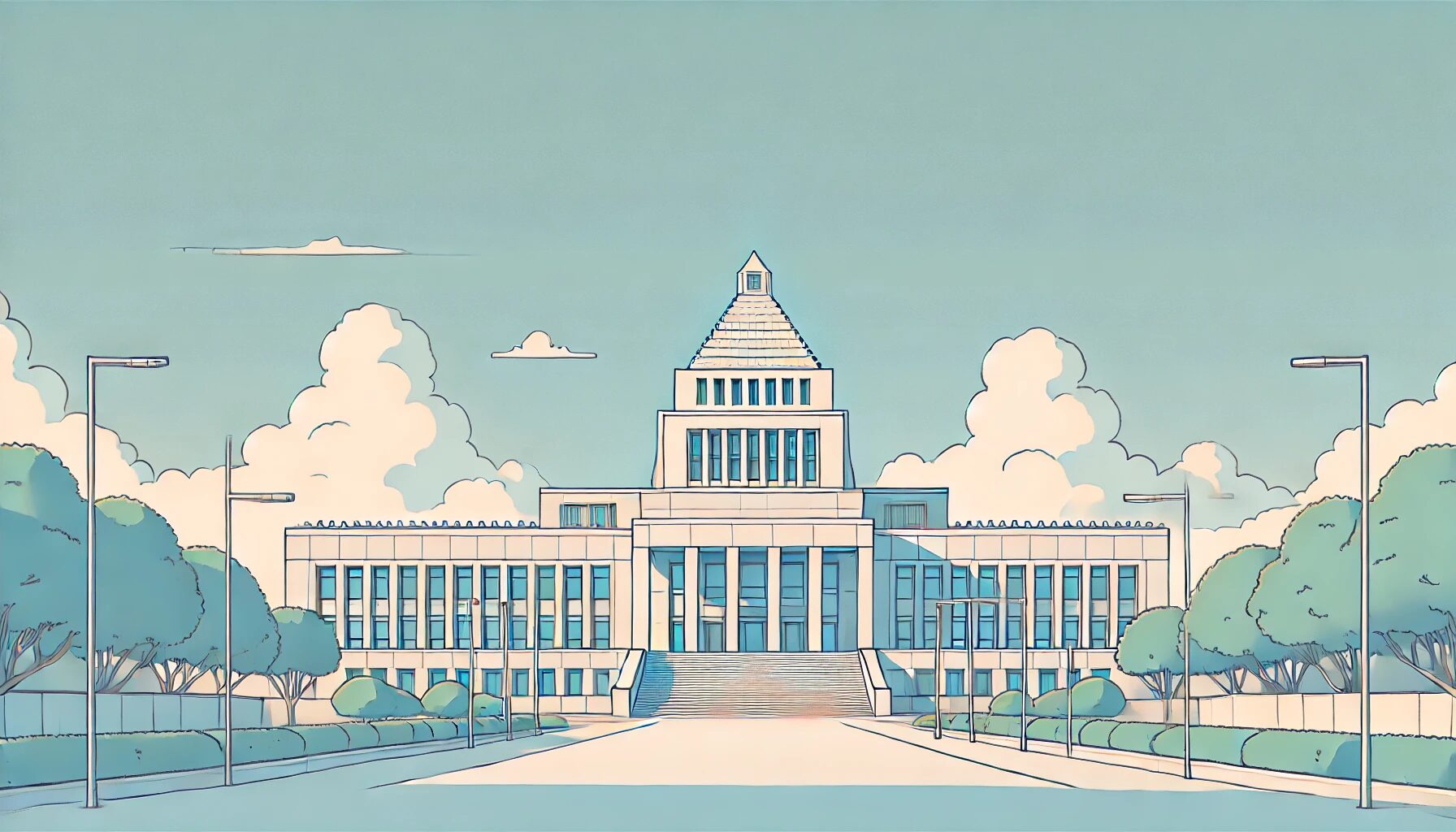





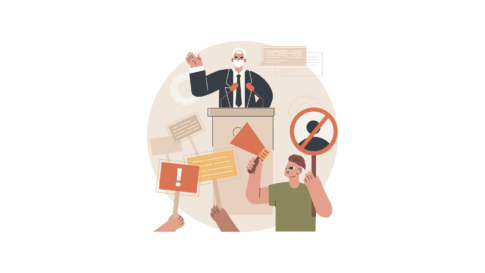

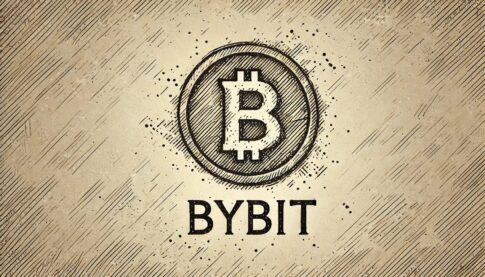





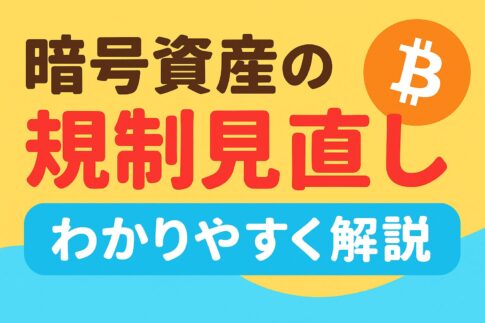



コメントを残す