ケンタッキー州の「ビットコイン権利法」と暗号資産ユーザーへの保護
ケンタッキー州では2025年3月、暗号資産ユーザーの基本的権利を明文化した「ビットコイン権利法」(州法HB701)が成立しました。
この法律により、同州の暗号資産ユーザーは具体的に次のような保護・恩恵を受けます。
- セルフカストディ(自己管理保管)の権利: 暗号資産を自分自身で保有・管理する権利が法的に保障されました。第三者のカストディアン(保管業者)を強制されることなく、自分の秘密鍵を保持できることを意味します。
- ノード運用の自由: ビットコインなどの暗号資産ネットワークのノードを自宅や事業所で稼働させる自由も明確に認められています。自らネットワークに参加し検証作業を行っても、これを理由に規制当局や他の権限から妨げられない保証です。
- 暗号資産利用に対する差別の禁止: 暗号資産の保有・使用を理由として、公的機関や企業から不利な扱い(サービス拒否や口座閉鎖など)を受けないよう保護する条項も含まれています。つまり、暗号資産を使うこと自体を理由にした差別的対応を州として禁止しました。
- マイニング(採掘)活動の権利保護: 暗号資産のマイニング事業に対しても権利が守られています。地域自治体がゾーニング(土地用途規制)を変更して暗号資産マイニング業者だけを締め出すことを禁じており、ビットコインマイナーが他のデータセンター同様に事業を営めるよう保証しています。
また、マイニング業者に対して送金業者(マネー・トランスミッター)のライセンスを要求しないことも明記されました。
ビットコインのノードやマイニングを行うこと自体が送金サービス提供とは見なされず、過度なライセンス規制から免除されています。 - マイニング・ステーキングの証券該当性の否定: ビットコインのマイニングやプルーフ・オブ・ステーク(PoS)によるステーキングは、有価証券の提供・販売とは見なさないことが法律で明確化されました。これにより、暗号資産のネットワーク維持活動が証券規制の対象外であると示され、ユーザーや事業者は証券法違反を問われるリスクから保護されます。
以上のように、ケンタッキー州のビットコイン権利法は暗号資産を「自己の資産」として保有・利用・運用する基本的自由を州法で保証するものです。
例えば、自分のビットコインを自身で保管し、それを使ってネットワークに参加したり決済に利用したりしても、州当局や他の法令によって不当に制限されたり罰せられたりしない安心感を与えています。
この法律は州議会下院で91対0、上院で37対0という全会一致で可決されており、州として暗号資産ユーザー保護に積極的な姿勢を示しました。
類似法案の他州および世界への波及
ケンタッキー州のような「暗号資産ユーザーの権利保護」立法は、米国の他州や世界各国にも波及する可能性があります。
実際、米国内の他州では既に類似の取り組みが進んでいます。
例えばオクラホマ州では2024年5月にケビン・スティット知事がケンタッキーとほぼ鏡写しの内容を持つビットコイン擁護法案に署名し法律が成立しています(※オクラホマ州の法案は2024年に全会一致で可決)。
また、ミシシッピ州やミズーリ州でも2023年初頭に、ビットコインのノード運用やマイニングの権利を住民に保障する法案が議会に提出されました。
これらの州法案には、地方自治体がビットコインマイニング施設だけを狙い撃ちした規制を行うことを禁止したり、マイナーに対する差別的な電力料金設定を禁じたりする条項が盛り込まれており、暗号資産関連事業が他業種と公平に扱われることを目指しています。
米国ではこのように、連邦レベルで明確な暗号資産規制が定まらない中、州ごとにユーザー権利を明文化し保護する潮流が生まれていると言えます。
世界全体に目を向けても、暗号資産の権利や利用を法律で認める動きが少しずつ広がっています。
代表的な例が中米エルサルバドルで、同国は2021年9月に世界で初めてビットコインを法定通貨として採用しました。
エルサルバドルの「ビットコイン法」により、ビットコインは法定通貨として 強制通用力を持ち、全国の事業者がビットコインによる支払いを受け入れることが義務化されています。
これにより国民はビットコインを公式な通貨として自由に利用でき、暗号資産ユーザーの権利が国家レベルで保障された例と言えます。
また、欧州連合(EU)も包括的な暗号資産規制であるMiCA(Markets in Crypto-Assets規則)を2023年に制定しました。
MiCAは暗号資産の発行者やサービスプロバイダに統一ルールを課すもので、2024年末以降段階的に適用が開始されます(2023年6月発効、主要規定は2024年末から適用)。
MiCA自体はユーザーの「権利法」といった性格ではありませんが、ホワイトペーパーの開示や取引所の資本要件などを義務付けることで投資家保護と市場の健全性向上を図っており、結果的に暗号資産ユーザーが安心して取引できる環境整備につながるものです。
加えて、スイスやアラブ首長国連邦(UAE・ドバイ)など暗号資産先進地域では、既存法の中で暗号資産を明確に位置づけたりライセンス制を導入したりすることで、ユーザーが合法的に暗号資産を保有・利用できる枠組みを整えています。
以上のように、ケンタッキー州のビットコイン権利法は単独の事例に留まらず、各地で進む暗号資産への法的対応の一端と言えます。
今後、他の米国州や国々でも、暗号資産ユーザーの基本的権利を直接保護する法律が成立したり、あるいは暗号資産を明確に合法化し利用者保護を図る包括的な規制枠組みが整備されたりする可能性があります。
アジア地域における暗号資産法整備の進展
特にアジア地域では、暗号資産に関する法整備が先行して進んでいる国・地域があります。
以下ではアジアの主要国を中心に、各国の進捗状況、法制度の内容、政府のスタンスを比較しやすいよう整理します。
日本(Japan)
- 進捗: 日本は2017年に世界に先駆けて改正資金決済法を施行し、暗号資産交換業者(取引所)に金融庁への登録を義務付けるなど基本的な規制を導入しました。
その後も度重なる流出事件や国際基準を踏まえ規制強化が図られています。2022年にはステーブルコイン(法定通貨価値連動型暗号資産)に関する法改正が成立し、2023年6月に施行されました。この改正により外国通貨建てのステーブルコインは「電子決済手段」と定義され、2023年以降、銀行や信託会社など一定の免許を持つ業者のみが発行できる仕組みになっています。 - 法制度の内容: 日本法ではビットコインなど暗号資産は有価証券ではなく「暗号資産」という独自の区分で扱われています。暗号資産の交換業を営むには内閣総理大臣(実務上は金融庁)への登録が必要で、無登録で営業すれば犯罪となります。また、改正資金決済法では利用者資産の分別管理や情報セキュリティ基準も定められており、取引所は顧客の暗号資産をオフライン保管することや、ハッキング被害に備えた準備金の確保などが求められます。さらに2023年の改正では、ステーブルコイン発行体を銀行・信託会社・資金移動業者に限定し、十分な法定通貨担保や償還請求権の保証を義務付けました。このように日本は早期から法的枠組みを整備しつつ、技術の発展に合わせてアップデートを続けています。
- 政府のスタンス: 日本政府はブロックチェーンやWeb3分野を経済成長戦略の一つに位置づけています。2022年には自民党内に「Web3プロジェクトチーム」を設置し、NFTやDAO(自律分散組織)も含めた総合的な政策検討を開始しました。政府方針として「分散型インターネット(Web3)の環境整備を経済の柱にする」と掲げられており、その一環として暗号資産の規制整備や税制見直しも進められています。ただし同時に、過去のハッキング事件や詐欺的ICOの問題を踏まえ、投資家保護やAML/CFT(マネロン・テロ資金対策)にも厳格な姿勢をとっています。例えば暗号資産に関する利益には厳しい税率が適用され、交換業者に対する検査・監督も他国に比べ厳密です。しかし近年はスタートアップ振興の観点から、企業保有するトークンの未実現利益課税の撤廃や、DAOの法人格付与に向けた法改正の検討など、イノベーションを阻害しないよう規制を見直す動きも出ています。総じて、日本のスタンスは**「健全な市場育成のために規制は厳格に、しかしブロックチェーン技術の可能性は国家戦略として推進」**というバランス重視の姿勢です。
香港(Hong Kong)
- 進捗: 香港は近年、暗号資産規制を大きく転換しました。2023年6月に改正「マネーロンダリング及びテロ資金調達防止条例(AMLO)」が施行され、仮想資産取引プラットフォーム(VATP)に対する包括的なライセンス制度が導入されました。これにより、従来プロ向けに限定されていた暗号資産取引が規制当局(証券先物委員会=SFC)の許可したプラットフォームにおいて個人投資家にも開放されています。施行当初、SFCはライセンス申請の受付を開始し、2024年にかけて多数の事業者が申請を行いました。また香港金融管理局(HKMA)はステーブルコイン規制にも取り組んでおり、2023年に方針を発表、2024年遅くに関連法案を立法会に提出する計画です。この新規制の下では、法定通貨に連動するステーブルコイン発行体に対し、100%準備資産による裏付けや最低資本要件(約2,500万HKD)、香港居住者向けの発行の場合はHKMAへのライセンス登録を義務付ける見通しです
- 法制度の内容: 現行の香港規制では、トークンを証券性トークン(証券トークン)と非証券トークンに分類し、それによって監督官庁が異なります。証券性のあるトークン(証券トークン)は証券法の規制対象でプロ投資家向けに限定されていますが、それ以外のビットコインなど一般的な暗号資産(バーチャル・コモディティ)はSFCの監督下で許可された取引所により個人にも提供可能です。新ライセンス制度の下で取引プラットフォーム(VATP)は、利用者資産のオフラインでのカストディ(保管)や厳格なKYC/AML手続き、トークンの上場審査基準の策定など、詳細なルールに従う必要があります。例えば、個人投資家が取引できるトークンは時価総額等の基準を満たした主要銘柄に限定され、また投資家へのリスク開示や知識テストの実施も求められています。無許可業者の取り締まりも強化されており、未ライセンスで営業する取引所は違法となります。
- 政府のスタンス: 香港政府は暗号資産・ブロックチェーン分野を今後の金融イノベーションの柱と位置づけつつも、リスク管理に重きを置く姿勢です。2022年に発表された金融サービス庁(FSTB)の政策声明では「国際金融センターとして香港は暗号資産ビジネスに対しオープンかつ包摂的である」と宣言しつつ、「イノベーションが持続可能に発展できるよう適時かつ必要なガードレールを設ける」と述べられています。この方針に沿って、規制当局は市場育成と投資者保護のバランスを取った制度設計を行っています。実際、香港政府はWeb3ハブとして海外企業誘致に積極的で、規制が整った安全な市場であることをアピールしています。一方で、中国本土では依然として暗号資産取引が禁止されていますが、香港はその枠外で**「監督された自由」を提供する戦略を採っています。総じて香港のスタンスは、「積極果敢な受け入れと厳格な規制の両立」**と言えるでしょう。
シンガポール(Singapore)
- 進捗: シンガポールはアジアで最も早くから暗号資産に明確な法制度を設けた国の一つです。2019年に「決済サービス法(PSA)」を制定し、2020年1月より暗号資産(デジタル決済トークン=DPT)取引業者に対するライセンス制度を開始しました。以降、大手取引所を含む数多くの事業者がMAS(金融管理局)にライセンス申請を行い、慎重な審査を経て承認されています。特に近年はライセンス交付のペースが加速しており、2024年11月時点で累計29社がDPTサービスプロバイダーとして正式認可を受けました。また、規制面の強化も進んでおり、2022年には決済サービス法改正で海外業者への規制適用やトラベルルール(送金時の情報通知)の導入を行い、2023~2024年には顧客資産のカストディ規則や利用者保護ガイドラインの施行が段階的に開始されています。
- 法制度の内容: シンガポールでは暗号資産サービス提供者はMASによる厳格なライセンス制・監督下にあります。DPTライセンスを取得した業者は、顧客資産の分別管理(利用者のデジタル資産を自社の資産と明確に分離し安全に保管)や最低資本金の確保、リスク開示、利益相反の回避などについて詳細な規則に従わねばなりません。2023年にMASが発表したガイドラインでは、取引所が顧客資産を信託保管することや、プラットフォーム破綻時に備えて資産を分別管理することなど、利用者保護のための具体的措置が定められています。さらに、ステーブルコイン規制にもシンガポールは先進的で、2023年8月に単一通貨建てステーブルコイン(SCS)の規制枠組みを世界に先駆けて確定させました。発行規模500万シンガポールドル超の主要ステーブルコイン発行体に対し、100%の準備資産と常時1:1で法定通貨への換金に応じる義務、定期的な監査報告を課す内容で、既にいくつかの企業がこの基準での発行を計画しています。これによりステーブルコイン市場の信頼性を高め、暗号資産エコシステム全体の安定性向上が図られています。
- 政府のスタンス: シンガポール政府は「スマート金融センター」戦略の下でブロックチェーンやデジタル資産の積極的な活用を推進しています。他方で、暗号資産の投機的な売買による消費者被害には敏感であり、個人投資家保護のため規制を厳しくする二面性があります。MASのメノン長官は2022年の演説で「デジタル資産のイノベーションにはイエスだが、暗号通貨での投機にはノーだ」という方針を明言しており、「両者は矛盾しない」と述べています。具体的には、個人向け規制の強化策として適性テストの導入や信用取引・レバレッジの禁止など「取引への摩擦を意図的に増やす」措置も検討されました。実際、MASは2022年に暗号資産サービスの一般向け広告を厳しく制限し(ATMからの撤去等)、2023年には取引所に対し顧客へのリスク情報開示と自己責任原則の徹底を求める指針を発出しています。総じてシンガポールのスタンスは、**「革新的技術や有望ビジネスは受け入れるが、射幸的な投機から国民を守る」**という明確なポリシーに基づいており、健全なマーケット育成と金融安定の両立を目指しています。
韓国(South Korea)
- 進捗: 韓国では2023年に暗号資産に関する初の本格的な包括法が成立しました。**「仮想資産利用者保護法」**と呼ばれるこの法律は、テラ(LUNA)暴落事件や国内取引所の相次ぐ破綻を受けて利用者保護の必要性が高まり、超党派の支持で成立したものです。2023年6月30日に国会で可決・成立し、充分な準備期間を経て2024年7月19日に施行されました。この法律制定により、韓国も暗号資産市場に法的基盤が築かれ、新たな段階に入っています。
- 法案・規制内容: 仮想資産利用者保護法の主眼は、その名の通り投資家(利用者)の保護と市場の公正性確保にあります。まず、法律の中で「仮想資産」の定義を明確化し、ゲーム内通貨やNFT、中央銀行デジタル通貨(CBDC)などは除外対象としています。そして暗号資産取引所など仮想資産サービス提供者(VASP)に対し、利用者資産を安全に管理する厳格な義務を課しました。具体的には、顧客から預かった法定通貨は信頼性の高い金融機関(銀行)に分別保管しなければならず、顧客の暗号資産についてもその80%以上をコールドウォレット(オフライン財布)で保管することを義務付けています。これは既存の情報保護認証(ISMS)基準で要求されていた70%より厳しい水準で、月次で監査されます。さらに、ハッキングやシステム障害による損失に備え、取引所はホットウォレット(オンライン保管分)の顧客資産額の少なくとも5%に相当する保険に加入するか準備金を積み立てることが求められます。こうした資産保護策に加え、相場操縦・インサイダー取引・作為的な出来高操作など不公正な取引行為に対する罰則規定も設けられました。違反者には刑事罰や課徴金が科されるため、暗号資産市場における違法行為の抑止が期待されています。
- 政府のスタンス: 金融当局(金融委員会・金融監督院)は本法律の成立に際し「仮想資産市場における秩序の確立と利用者保護の画期的な一歩」と評価しており、その姿勢は一貫して投資家保護と市場健全化の重視にあります。韓国は2017年末にICO(仮想通貨の新規発行)を全面禁止するなど厳しい対応を取った時期もありましたが、尹錫悦政権に代わってからは規制によるコントロールへと方針転換しています。尹大統領自身、選挙公約でICO解禁の検討や暗号資産課税の見直しを掲げており、政府内でも健全なブロックチェーン産業育成のためには一律禁止でなく適切なルール作りが必要との認識が広がりました。現在のスタンスは、違法行為や投機的バブルは厳格に抑える一方で、ブロックチェーン技術やデジタル資産ビジネス自体の発展は前向きに捉えるというものです。例えば証券性のあるトークンについては既存の資本市場法で取り込み(セキュリティ・トークンの合法化)、証券性のない暗号資産については上記の利用者保護法で健全な市場を育てる、といった二本立て戦略が進んでいます。総じて韓国政府の姿勢は「必要な規制は厳しく、しかしブロックチェーン産業の発展余地は肯定する」方向へシフトしており、アジア有数の暗号資産市場として国際的な整合性も意識した法整備を進めていると言えます。
各国で法制度のアプローチは異なりますが、暗号資産を巡るルール形成が活発に進んでいる点は共通しており、こうした動きは今後も世界的に拡大していくと予想されます。




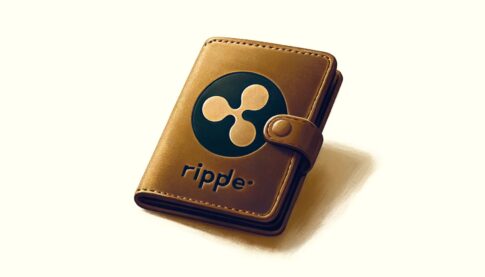






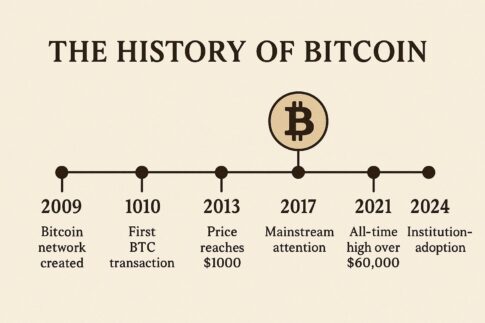
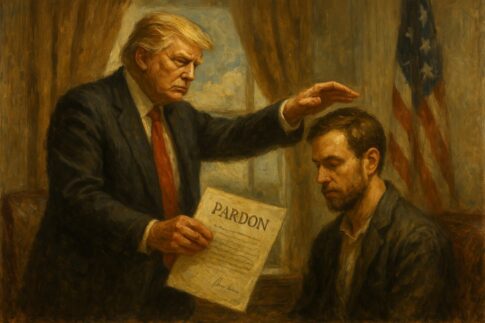
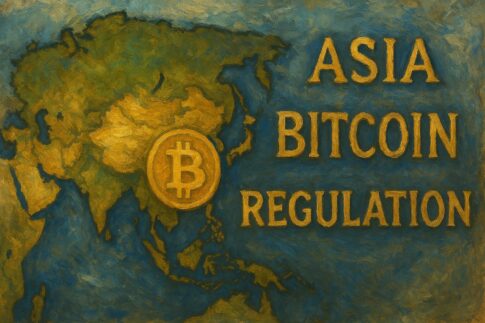

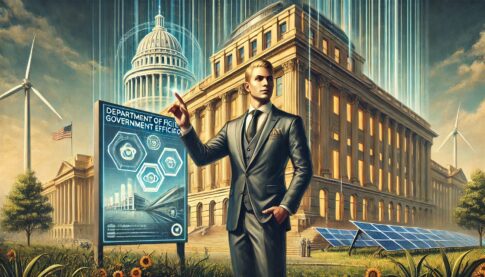

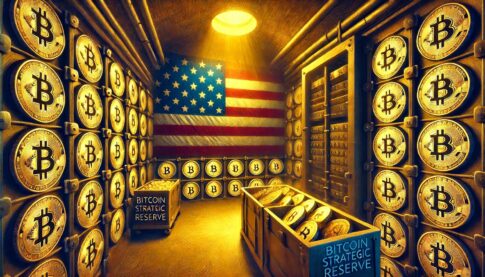
コメントを残す