経済ニュースや社会の授業で、「先進国」や「新興国」という言葉を耳にしたことはありませんか?
先進国と新興国は、国の経済的な発展段階を示す言葉です。
ざっくり言うと、先進国は経済が高度に発展し人々の生活水準が高い国、新興国は経済発展の途中にあり今後大きな成長が期待される国を指します。
本記事では、先進国と新興国の定義や特徴、代表的な国の例、抱える課題や強み、国際社会における役割の違いについて、中学生にもわかるようにやさしい言葉で解説します。
最後に、時代とともに国の位置づけが変化することもある点にも触れます。
先進国と新興国の定義と特徴
まずは先進国と新興国とは何か、その定義と特徴を見ていきましょう。
国際的に厳密な決まりはありませんが、一般的なイメージや指標に基づいて説明します。
先進国の定義・特徴
先進国(せんしんこく)に明確な国際基準はありませんが、一般には「経済的に豊かで暮らしが整っている国」というイメージで捉えられています。
例えば一人ひとりの平均的な収入が高く、食事や住む場所、医療や教育など生活水準が全体的に高いことが特徴です。
また、工業やサービス業などの産業が高度に発達し、インフラ(社会基盤)も整備されています。
政治的にも安定しており、法律や行政の仕組みがしっかりしている国が多いです。
先進国を判断する客観的な基準は国によって様々ですが、よく使われる指標には1人当たりのGDP(その国の経済規模を人口で割った指標)や人間開発指数(平均寿命や教育水準などの総合指標)などがあります。
これらが高い値を示す国は、先進国とみなされる傾向があります。
ただし世界共通の先進国の定義はなく、国連や世界銀行、IMF(国際通貨基金)など機関ごとに分類の基準が異なるのが実情です。
もう少し具体的に見てみると、先進国の多くは北アメリカや西ヨーロッパ、東アジア・オセアニアなどに位置しています。
歴史的に見ても、19世紀から20世紀にかけていち早く工業化(産業革命など)を成し遂げた国々や、かつて植民地支配などで富を蓄えた欧米の列強と呼ばれた国々が、現在の先進国の中心となっています。
また、日本やシンガポール、韓国のように、戦後の高度経済成長によって先進国の仲間入りをした国もあります。
先進国の特徴まとめ
- 経済規模・所得が大きい: 国全体の経済が大きく、一人当たりの所得も高い傾向(例:日本の一人当たりGDPは約4万ドル超)。
- 生活水準が高い: 教育や医療が充実し、平均寿命も長い。安全な水や電気がほぼ全国民に行き渡っている。
- 産業が高度: 第一次産業(農林水産業)よりも、工業や情報通信産業、金融・サービス業など高付加価値の産業が中心。技術力が高く、研究開発が盛ん。
- インフラが整備: 道路・鉄道・電力・通信網などのインフラストラクチャーが全国的に発達。都市も計画的に整備されている。
- 政治・社会の安定: 政府の仕組みが安定し、法制度も整っている。紛争や内戦も少なく、表現の自由など民主的な社会制度が確立している国が多い。
こうした条件を概ね満たす国が先進国と呼ばれます。
しかし、経済規模が大きくても平均的な豊かさが不足している国は先進国とみなされません。
例えば、中国やインド、ブラジルなどは経済全体の規模では世界上位ですが、国民一人当たりでは豊かさが中位以下で地域格差も大きいため、先進国には含まれません。
このように、「一部の人が非常に裕福でも国民全体で見た生活の質が高くなければ先進国とは言いにくい」ということです。
新興国の定義・特徴
新興国(しんこうこく)とは、簡単に言うと「現在は先進国ほど豊かではないものの、これから経済成長が期待できる国」のことです。
英語では「エマージング・カントリー(Emerging Country)」とも呼ばれます。
新興国には明確な定義はありませんが、一般に政治や経済がまだ発展途上である一方、経済成長率が高く将来の発展が見込まれる国々を指します。
つまり、「今まさに興(おこ)りつつある」国というイメージです。
新興国は広い意味では「発展途上国(はってんとじょうこく)」の一部に含まれます。
発展途上国とは先進国に比べ経済水準が低い国全般を指しますが、その中でも特に近年高い経済成長を遂げている国々を新興国と呼ぶことがあります。
例えば、アジアや中南米、アフリカの一部で著しい工業化や経済改革が進み、急速に豊かになりつつある国々が新興国にあたります。
一方、同じ途上国でも経済成長が停滞し極度の貧困に苦しむ国々は「後発開発途上国(Least Developed Countries)」と呼ばれ、新興国とは区別されます。
新興国と後発途上国では、経済規模や人々の生活水準に大きな差があることに注意しましょう。
新興国の特徴まとめ:
- 経済成長率が高い: GDPが毎年5~10%以上伸びるような高成長を遂げている国が多いです。先進国の成長率(せいぜい1~3%程度)と比べると顕著です。
- 若い人口構成: 子どもの割合が高く、生産年齢人口(働く世代)が増加しています。人口ボーナスと呼ばれる、人口構成が経済成長に有利な時期にある国も多いです。
- 都市化と産業発展: 農村から都市への人口移動が活発で、急速に都市化が進んでいます。
工場が建設され工業化が進行中で、自動車や電子機器などの製造業が成長しています。サービス業も徐々に発達し、中間層(中流階級)の消費が拡大しています。 - インフラ整備途上: 経済成長に伴い道路や港湾、電力・通信などのインフラを整備している段階です。ただし地方では未整備の地域も多く、停電や交通網の未発達といった課題も残ります。
- 制度が整いつつある: 政治体制や法律も改革が進んでいますが、先進国に比べると政治・経済の安定性は低い場合があります。物価の変動や政府の政策変更が頻繁に起こる国もあります。
以上が新興国の一般的な特徴です。
「新興」という言葉のとおり、今まさに経済がぐんと伸びて勢いのある国々と言えます。
例えば中国やインドは広大な国土と膨大な人口、豊富な資源を背景に高成長を実現しており、新興国を代表する存在です。
一方で、政治が安定しなかったり都市と地方で格差が大きかったりと、発展途上ならではの問題も抱えています。
世界の代表的な先進国と新興国の例
では、具体的にどの国が先進国でどの国が新興国なのでしょうか。
世界にはおよそ200近い国がありますが、そのうち先進国とみなされるのは約30~40か国程度と言われます。
残りの多くは広義の発展途上国であり、その中には経済成長が著しい新興国も含まれます。
主な先進国の例
アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、日本などのG7(先進7か国)は典型的な先進国です。
この他にもヨーロッパの多くの国(スペイン、スウェーデン、スイスなど)、オーストラリアやニュージーランド、シンガポール、韓国なども先進国に数えられます。
国際機関の定義によって多少異なりますが、IMFでは北米・欧州・アジア太平洋など39の国と地域を「先進国(Advanced Economies)」と分類しています。
日本もその一つです。
主な新興国の例
新興国としてよく名前が挙がるのがBRICS(ブリックス)と呼ばれる5か国です。
BRICSとはブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)、南アフリカ(South Africa)の頭文字を組み合わせた言葉で、いずれも経済成長が著しい新興経済大国として注目されてきました。
これら5か国は広い国土と多い人口を持ち、天然資源にも恵まれており、21世紀に入り急速に経済力を伸ばしています。
またBRICS以外にも、東南アジアのインドネシアやマレーシア、南米のメキシコ、中東のサウジアラビア、アフリカのナイジェリアなど、地域ごとに有力な新興国が存在します。
国際的な会議では、中国やインド、ブラジル、南アフリカ、メキシコなどが新興国の代表格としてG20サミットなどに参加しています。
世界の先進国(紫色)と発展途上国(オレンジ色・赤色)の分布図です。
紫色の国々が経済的に高度に発展した先進国を示しています。
オレンジ色や赤色で示された国々が、発展途上国(新興国を含む)です。
水色の国々は「先進国と途上国の中間段階」に位置する国々で、旧ソ連の東ヨーロッパ諸国や中国など先進国に近い水準まで発展した国を表しています。
先進国は北半球に多く、途上国はアジア・アフリカなど南半球に多い傾向が一目でわかります。
このように世界地図で見ると、経済発展の度合いによる国の分類が地理的にもある程度偏りがあることがわかります。
先進国と新興国が抱える課題と強み
先進国と新興国はそれぞれ異なる強みを持つ一方、異なる課題(問題点)にも直面しています。
ここでは、先進国と新興国それぞれの主な強みと課題を整理してみましょう。
先進国の強みと課題
先進国の強み: 先進国は長年の経済発展の中で培われた豊富な資本と高度な技術力を持っています。
大学や研究機関が多く、科学技術のイノベーション(革新)を起こしやすい土壌があります。
また、国民の教育水準が高く、優れた人材が豊富です。
法律や社会制度が整っており、ビジネスをする上で信頼性の高い環境があります。
加えて、国内の市場(消費者)が豊かで成熟しているため、高品質な製品やサービスが生み出されやすいです。
これらにより、先進国は世界経済の中で安定した成長と豊かな社会を実現してきました。
先進国の課題: 一方で先進国には経済成長の鈍化という課題があります。
すでに物やサービスが行き渡り市場が成熟しているため、年々大きく経済を成長させるのが難しくなっています。
例えば日本や西ヨーロッパ諸国では、高齢化により働く人の割合が減り、生産力の維持が難しくなっています。
人口が減少することで国内市場も縮小し、新しい産業を育てないと成長が止まってしまいます。
また、豊かさを維持するためのコストも高く、労働者の賃金や物価が高いため企業の競争力を保つのが大変です。
さらに、豊かな社会ゆえにエネルギー消費も多く、環境問題(地球温暖化など)への責任も大きいという課題があります。
先進国政府はこうした課題に対処するため、イノベーション促進や年金・医療制度の改革、持続可能な開発(SDGs)の推進などに取り組んでいます。
新興国の強みと課題
新興国の強み: 新興国は何と言っても勢いのある経済成長が最大の強みです。
高い成長率で経済規模を拡大しており、世界の市場としても存在感を高めています。
人口が多く若いことから、労働力が豊富で人件費も先進国より低い場合が多く、製造業などで国際競争力を持ちやすいです。
また、「これから」消費者層になる中間所得層が増えており、自動車や家電製品、スマートフォンなど新しい製品・サービスに対する需要の伸びしろがあります。
豊富な天然資源を持つ国も多く(例:ロシアの石油、チリの鉱物、中国のレアアースなど)、資源輸出による収入を成長の原動力にできる点も強みです。
さらに、まだ市場が成熟しきっていない分野では新規参入の余地が大きく、国内外の企業にとってビジネスチャンスが広がっています。
新興国の課題: 新興国は発展の途上ならではの課題も抱えています。
まず政治・経済の不安定さです。
政権が交代したり政策が急変したりと、社会が不安定になるリスクがあります。
経済面でもインフレ(物価上昇)や通貨価値の変動が激しい場合があり、安定した成長を続けるための制度づくりが課題です。
また、急速な成長の陰で格差や貧困も大きな問題です。
都市部は豊かになっても地方や農村部は取り残され、貧しい人々が依然として多い国もあります。
インフラ未整備による交通渋滞や停電、水不足など生活上の不便も残っています。
さらに、教育や医療の水準が十分でなく、人材育成や国民の健康増進もこれからの課題です。
環境面でも、工業化による大気汚染や森林破壊などが進行しやすく、持続可能な開発との両立が問われています。
新興国はこれらの課題を乗り越えることで、真の意味で豊かな国へとステップアップしていく必要があります。
先進国と新興国の関係性・国際社会での役割
先進国と新興国はお互いに影響を与え合い、国際社会の中でそれぞれ重要な役割を担っています。
その関係性や役割の違いについて見てみましょう。
経済面の関係: 先進国と新興国の経済は相互依存の関係にあります。
先進国の企業は新興国に工場を建てて製品を生産したり、新興国の市場に商品を輸出したりしています。
一方、新興国は先進国から資本(投資)や技術を導入し、自国の産業発展に活かしています。
また、新興国は原油や鉱物資源、農産物などの資源供給地として先進国経済を支え、逆に先進国は新興国にとっての巨大な消費市場となっています。
このように貿易や投資を通じて、先進国と新興国は深く結びついているのです。
国際協力と援助: 先進国は経済力が高いため、国際社会では新興国や途上国への支援役を果たすことが多いです。
例えば日本や欧米諸国は、発展途上国に対して技術協力や資金援助(ODA: 政府開発援助)を行い、インフラ整備や教育・医療の充実を手助けしています。
これは人道的な目的だけでなく、世界全体の安定と繁栄が自国の利益にもつながるという考えからです。
一方、新興国側も先進国から援助を受け入れるだけでなく、近年では南南協力(途上国同士の協力)や新興国同士の経済連携を強めています。
例えば、中国やインドなどはアジアやアフリカの他の途上国に投資を行い、インフラ建設を支援する動きを見せています。
国際機関・会議での役割: 冷戦後しばらくは、アメリカやヨーロッパ、日本など先進国が集まるG7(先進国首脳会議)が世界経済のルール作りを主導してきました。
しかし21世紀に入り新興国の力が増すと、主要な新興国を含めたG20(20か国・地域の首脳会議)が重要性を増しました。
G20には先進国に加え、中国、インド、ブラジル、南アフリカ、メキシコ、サウジアラビア、トルコなど新興国が参加し、世界経済や地球規模課題について議論します。
つまり、世界のリーダーシップが先進国だけでなく新興国にも広がっているのです。
国連などでも、新興国の発言力が高まっており、気候変動対策や貿易ルール作りなどで先進国と新興国が協調・交渉しながら進めるケースが増えています。
競争と協調: 国際社会では、先進国と新興国は時に利害が対立することもあります。
例えば、温室効果ガスの削減目標では、歴史的に排出の多い先進国と、これから発展する権利を主張する新興国で意見がぶつかることがあります。
また、貿易の面でも自国の産業を守るため関税をめぐって争う場合があります。
しかし基本的には、地球規模の課題(気候変動、感染症対策、平和維持など)は先進国・新興国が協力して取り組まなければ解決できないため、対話と協調が重視されています。
新興国が国際的な責任を担う場面も増え、先進国もそれを支援・牽制しつつ共に歩んでいく関係へと変化しています。
時代とともに変化する国の位置づけ
最後に、国が先進国か新興国かという位置づけは固定的なものではなく、時代とともに変化しうることを押さえておきましょう。
歴史を振り返ると、現在先進国と呼ばれる国々も昔から先進国だったわけではありません。
例えば日本やドイツ、フランスといった国々も、産業革命以前の18〜19世紀には経済規模が小さく「新興国」的な立場だった時期があります。
20世紀後半にはアジアの韓国やシンガポールが急成長を遂げ、新興国から先進国に近い水準へと発展しました。
韓国は1960年代までは開発途上国でしたが、2000年代にはOECD加盟国となり、今では一人当たり所得で世界上位に入るほどです。
逆に、一時は豊かだった国が経済的に停滞してしまう例もあります。
例えばアルゼンチンは20世紀初頭には世界有数の裕福な国でしたが、その後の政治経済の混乱で低迷し、現在では新興国とみなされています。
またギリシャはEU加盟国で先進国とされていましたが、2000年代末の金融危機で経済が悪化し、一部の評価機関では「先進国から新興国へ格下げ」とされたこともありました。
このように、国の経済力や社会状況は時とともに変わります。
新興国が成長して先進国の仲間入りを果たすこともあれば、先進国が停滞して相対的地位が下がることもありえます。
また、新たな技術や世界情勢の変化によって、従来の先進国と途上国の境目があいまいになることも指摘されています。
例えばデジタル技術の普及により、一部の途上国では携帯電話やモバイル決済が急速に広がり、金融サービスの面では先進国を飛び越えて発展する「リープフロッグ型」の事例も出てきています。
今後も国際社会の勢力図は動いていくため、「先進国」「新興国」という区分も絶対的なものではなく変化し続ける概念なのです。
まとめ
先進国と新興国の違いについて、定義や特徴から国際社会での役割まで幅広く解説しました。
先進国とは経済や生活水準が高く安定した国々であり、新興国とは経済発展の途中にあって高い成長が期待される国々です。
それぞれに強みと課題があり、互いに影響し合いながら世界の経済や社会を動かしています。
現在の先進国もかつては新興国だったことがあり、今の新興国も将来先進国に仲間入りする可能性があります。
国の発展段階は固定ではなく、時代とともに移り変わるものです。
私たちがニュースを見るときも、「この国は先進国だからこういう状況なんだ」「新興国だからこういう課題があるんだ」と背景を考えると理解が深まります。
世界の国々の違いを知ることは、国際社会の動きを学ぶ上で大切です。
ぜひ今回の解説を参考に、地理や公民の勉強やニュースの理解に役立ててくださいね。
【参考資料】先進国と新興国に関する定義や統計データ:外務省「OECDの概要」、内閣府「世界経済の潮流」、池上彰「先進国と新興国のいま」など。

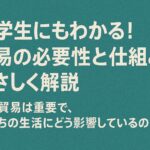

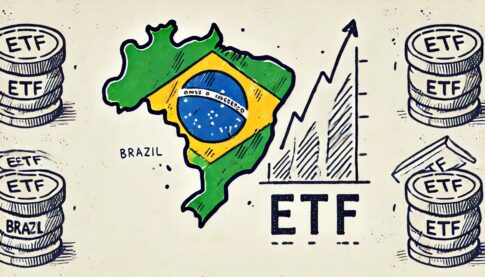

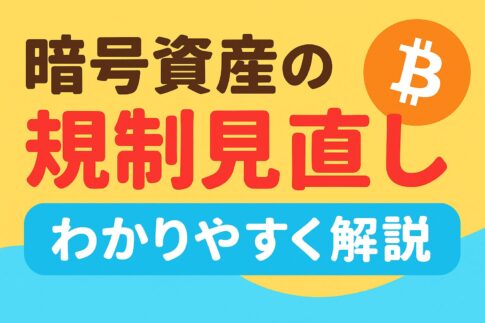





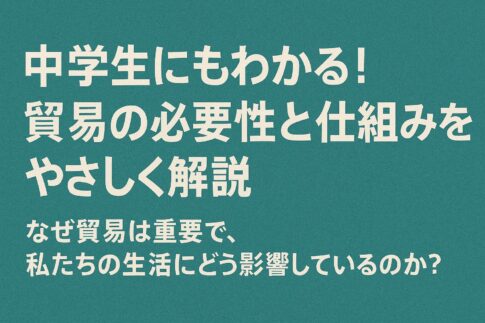

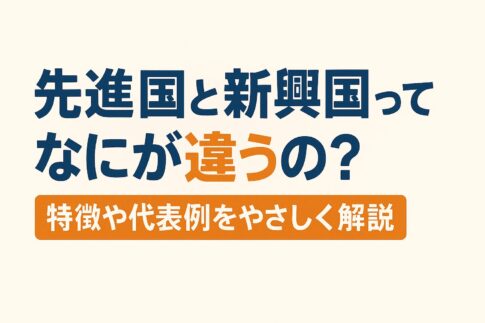




コメントを残す