2020年頃から、中央集権的な管理者を介さずに金融サービスを提供する分散型金融(DeFi:Decentralized Finance)が注目を集めています。
DeFiは、次世代のインターネットの概念である「Web3(ウェブ3)」を構成する重要な要素の一つとされています。
本記事では、DeFiの全体像をまとめ、どのようなサービスが提供されているのかを確認します。
さらに、DeFiの重要な仕組みである「イールドファーミング」と「流動性マイニング」についても詳しく解説します。
これらの仕組みがどのようにしてユーザーに利益をもたらし、DeFiエコシステムを支えているのかを探っていきましょう。
DeFiの基本概念と仕組み

DeFiは「Decentralized(分散型)」という言葉の通り、中央集権的な管理者なしで金融サービスを提供する仕組みのことを指します。
例えば、お金の貸し借りを行う際に、従来の金融システムでは銀行が仲介者として存在し、貸す人と借りる人をつなぐ役割を果たしています。
しかし、DeFiではプログラムによって、銀行などの仲介者を介さずに金融サービスを実行することが可能です。
これにより、銀行が倒産するリスクや仲介者による不正行為のリスクが減少しますが、自己責任での資産管理が必要となり、ハッキングや詐欺のリスクも存在します。
DeFiが必要とされる理由
DeFiが注目される理由は、「中央集権的な管理者なしで金融サービスを提供する」ことが多くの利点をもたらすためです。
銀行アクセスの問題
日本では金融サービスにアクセスできないことは少ないですが、海外では銀行口座を持てない人が多くいます。
銀行口座を開設できないと、身分を怪しまれたり、融資を受けられなかったりすることがあります。
しかし、DeFiではインターネットにアクセスできる環境があれば、誰でも金融サービスを利用できます。
管理者による制限の問題
金融サービスに管理者がいると、管理者の権限によって銀行口座が突如使えなくなったり、お金を引き出せなくなったりする事態が発生することがあります。
例えば、2021年1月に米国のゲームストップ社の株(GME)が乱高下する中、スマホ証券アプリを提供するロビンフッド社が一方的に取引を停止し、個人投資家が取引できなくなったことが問題視されました。
取引の柔軟性の問題
従来の金融サービスでは営業時間が限られていることや、送金に時間がかかることなどの問題があります。
DeFiはこれらの問題を解決し、人々がいつでもどこでも金融サービスにアクセスできるようにします。
DeFiはこうした問題を解決し、人々が金融サービスに自由にアクセスできる世界を目指しています。
DeFiの代表的なサービス

DeFiにはさまざまなサービスが存在し、以下のような有名なプロジェクトがあります。
ステーブルコイン
MakerDAOはステーブルコインプロジェクトの代表例です。
ステーブルコインは、価値が安定している暗号資産で、MakerDAOは米ドルと価値が連動するDAI(ダイ)を発行しています。
これにより、銀行口座を持たない人々でも安定した価値の暗号資産を利用できるようになっています。
分散型取引所(DEX)
Uniswapは分散型取引所(DEX)の代表例です。
DEXは、中央集権的な取引所とは異なり、ユーザー同士が直接取引を行うことができます。
これにより、取引の透明性とセキュリティが向上します。
デリバティブとレンディング
Synthetixはデリバティブを提供するDeFiプロジェクトです。
デリバティブとは、原資産の価格に基づく金融商品で、リスクヘッジや投機目的で利用されます。
Compound Financeは暗号資産レンディングプラットフォームで、ユーザーが暗号資産を貸し出すことで利息を得ることができます。
リキッドステーキング
Lidoはリキッドステーキングの代表的なプロジェクトです。
リキッドステーキングとは、暗号資産をステーキングして代替資産を受け取り、他のDeFiサービスで利用できる仕組みです。
ステーキングとは、暗号資産(仮想通貨)を特定のブロックチェーンネットワークに預け入れ、そのネットワークの運営や取引の承認に参加することで報酬を得る仕組みのことです。
これは、ブロックチェーンの一種である「プルーフ・オブ・ステーク(Proof of Stake、PoS)」という仕組みに基づいています。
例えば、イーサリアムを預け入れるとstETHというトークンを受け取り、それを他のサービスで活用できます。
通常のステーキングでは、一度暗号資産を預け入れると一定期間引き出すことができない「ロック期間」があります。この期間中は、預け入れた資産を他の取引や投資に利用することができません。
一方、リキッドステーキングでは、預け入れた暗号資産に代わる代替資産(例:stETH)を受け取ることができます。
この代替資産は、他のDeFiサービスで利用することができ、流動性を保ちながらステーキングの報酬を得ることが可能になります。
DeFiの新しい仕組み
イールドファーミング(Yield Farming)
イールドファーミングとは、ビットコインやイーサリアム、テザー(USDT)などの暗号資産をプラットフォームに預けることで流動性を提供し、利息を獲得する仕組みです。
例えば、Compound Financeでは貸した暗号資産に対して金利手数料を受け取ることができます。
流動性マイニング(Liquidity Mining)
流動性マイニングとは、DeFiプロトコルに参加する報酬としてガバナンストークンを受け取る仕組みです。
例えば、Compound Financeでは暗号資産を貸し出すことで利息とともにガバナンストークン(COMP)を受け取ることができます。
DeFiのリスクと注意点
DeFiにはいくつかのリスクが存在します。代表的なものは「ハッキング」と「インパーマネントロス」です。
ハッキング
DeFiはプログラムで運用されており、資金の運用額やコードが公開されています。
これにより、ハッカーがコードの脆弱性を発見し、攻撃するリスクがあります。
DeFiには法規制が及んでいないため、ハッキングで資金が失われても弁済されることは少ないです。
インパーマネントロス(Impermanent Loss)
インパーマネントロスとは、DeFiサービスで流動性プールにトークンを預けた際に、トークンの価格変動によって発生する損失のことです。
価格変動が大きいと損失の割合も大きくなります。
注目プロジェクトとTVL
DeFiプロジェクトの注目度を測る指標として「TVL(Total Value Locked)」があります。
TVLはスマートコントラクトにロックされた資金の総額を示しており、プロジェクトの人気や信頼性をある程度把握するための指標です。
例えば、リキッドステーキングプロジェクトのLidoは2024年3月末時点でTVLが約351億ドル(約5兆3250億円)と最も多く集めています。
まとめ
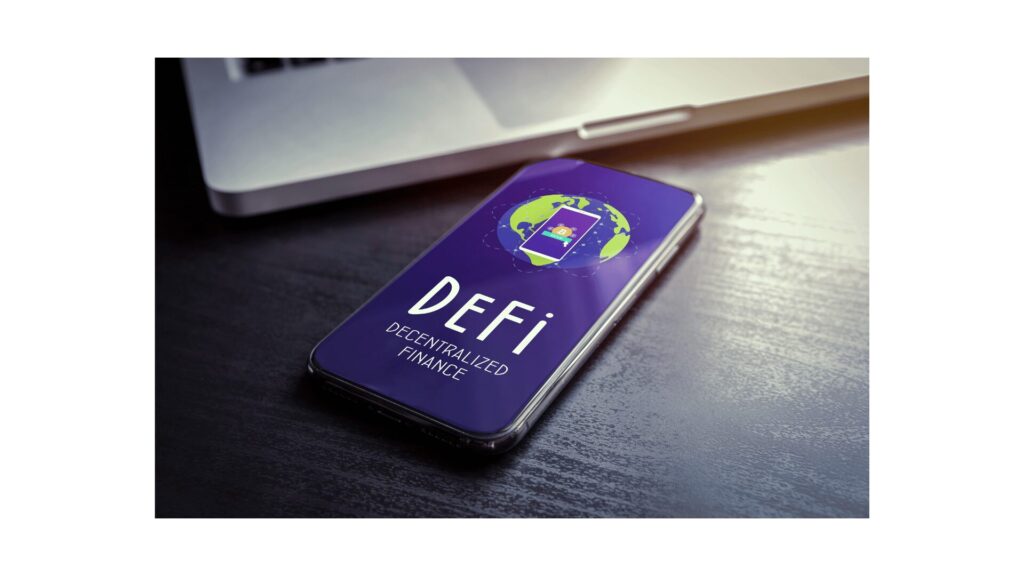
DeFi(分散型金融)は、伝統的な金融機関のような中央集権的な管理者がいない仕組みを通じて、金融サービスを提供するシステムです。
このシステムでは、ブロックチェーン技術が活用され、ユーザー間で直接的な取引が可能になっています。
2024年3月のデータによると、リキッドステーキングというサービスが特に人気を博しています。
リキッドステーキングは、ユーザーが暗号資産をステーキングすることで報酬を得られる一方で、ステーキングした資産を他の投資にも流動的に利用できるというメリットがあります。
さらに、イールドファーミングや流動性マイニングのような仕組みも導入されており、これらはユーザーがプラットフォームに資金を提供することで金利収入や新しいトークンを獲得できる方法です。
これらの魅力的な報酬のおかげで、多くの参加者がDeFi市場に引きつけられています。
しかし、DeFiにはリスクも伴います。主なリスクには、ハッキングによる資金の損失や、価格変動によって流動性プールが影響を受ける「インパーマネントロス」という現象があります。
これらのリスクは、資産を失う可能性があるため、DeFiサービスを利用する際には十分な情報収集と注意が必要です。
どのサービスに参加するかを決める前に、そのリスクを理解し、慎重に行動することが求められます。
GMOインターネットグループ(東証一部上場)の【GMOコイン】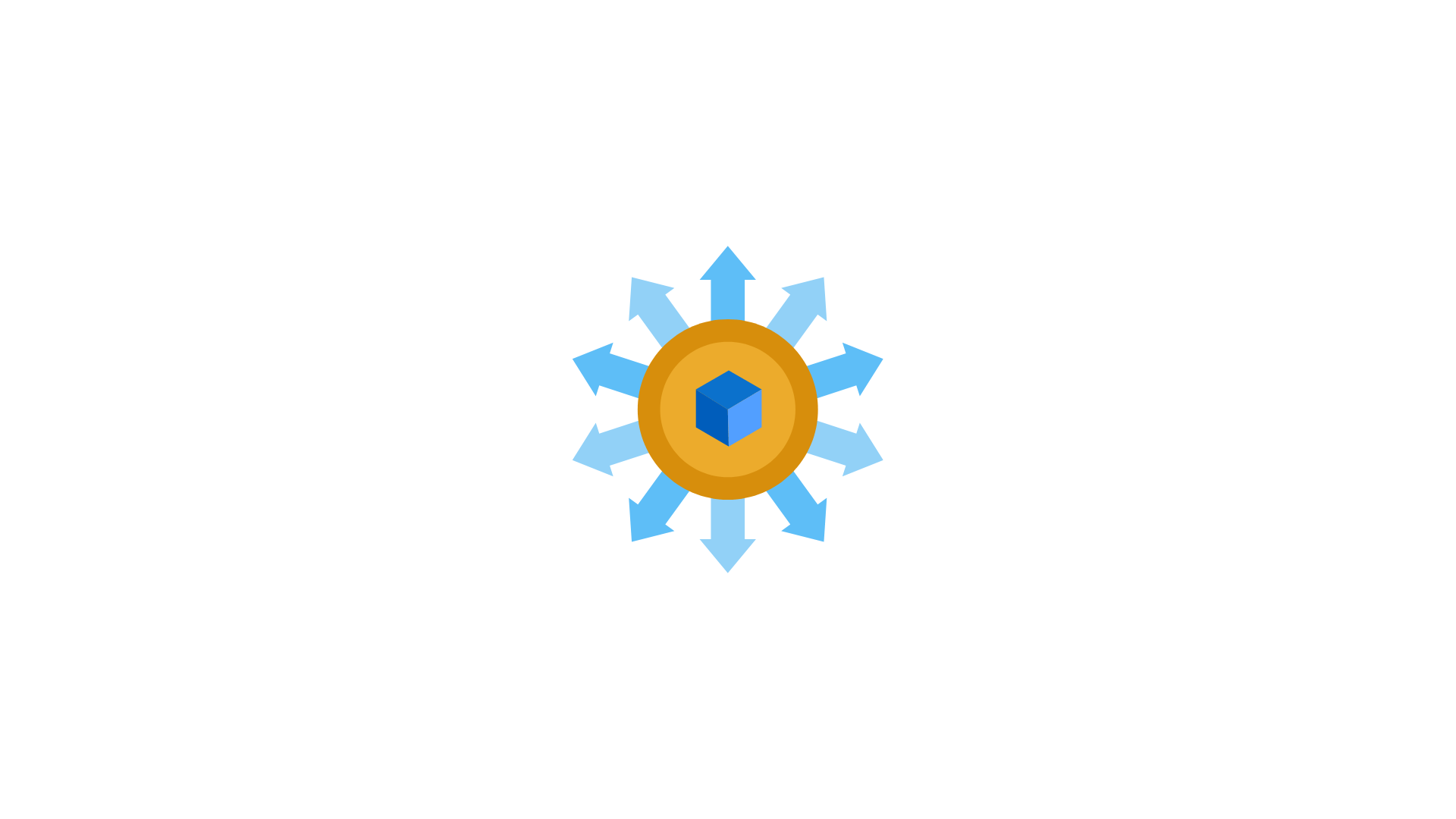






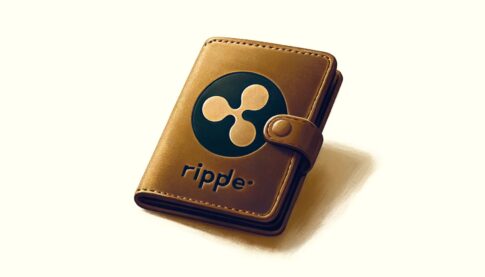




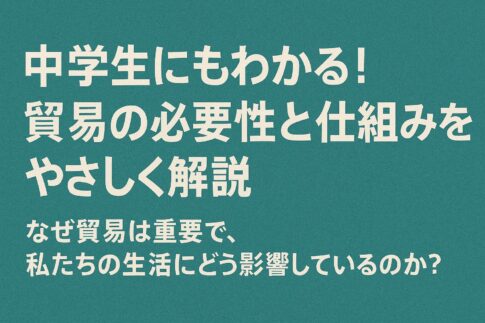

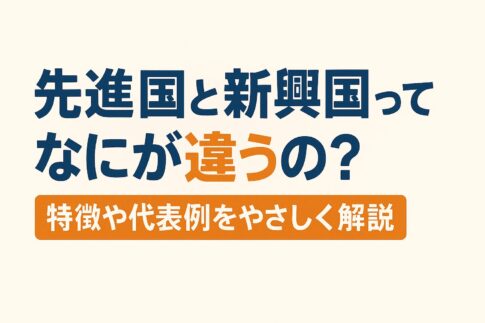




コメントを残す