GDPってニュースでよく耳にするけど、実際何のことかピンとこない…そんな人も多いのではないでしょうか?
GDPは「国内総生産」と呼ばれ、国の経済を語る上では必須のキーワードです。
前回の基礎編では、GDPが「国内で交換されたすべての商品やサービスの総額」だと学びましたね。
でも、これだけ聞いてもまだ「GDPって結局何?どうやって測ってるの?」と疑問が残りますよね。
実際、GDPを測る方法は1つではなく、3つもあるんです!
ちょっと難しく聞こえますが、必ずわかるように専門用語を噛み砕きながら解説するので、一緒に学んでいきましょう!
この記事では、GDPとは何かをおさらいしつつ、GDPの測り方を初心者向けにやさしく解説します。
経済学ではGDPを計算する方法が「生産」「支出」「分配」の3つあるとされていますが、それらを数値例や例題を使って専門用語も噛み砕きながら解説します。
また、名目GDPと実質GDPという異なる2種類のGDPの違いや、GDPが私たちの経済と生活にどう関わっているかも取り上げて解説していきます。
さっそく、GDPの世界を一緒に見ていきましょう!
GDPとは?簡単におさらい
GDPは「Gross Domestic Product」の略で、日本語では「国内総生産」と訳されます。
ずばりやさしく言うと、「国の内部で作られたすべての生産品の総額」ということ。
もう少しかみくだいて言うと、「国内」というのは日本の国の中、「総生産」というのは“すべて合わせて作り出したもの”を意味します。
つまり、GDPとは、一国内で一年間に新たに生み出された商品やサービス(最終的に消費されるもの)をすべて合計した金額のことです。
たとえば、毎日私たちが買う食料品や文房具、お店やご飯屋さんで払うお金、そういったものがすべてGDPに含まれています。
ここで言う「買う」「払う」というのは、言い換えれば「国内で生産されたものを消費した」ということ。
国が一年でこれだけの金額のものを生み出し、人々がそれを買うことができたんだ!と表しているのがGDPなのです。
GDPが大きいと「その国は経済のパワーが大きい」ことを意味し、世界で一番GDPが大きいのは米国(アメリカ)、次いで中国、そして第3位が日本です。
また、GDPの増減を「経済成長率」と呼び、GDPが毎年増え続ければ「経済成長中」、縮小すれば「リセッション(景気後退)」と言ったりします。
GDPの数字は、国の経済の「スケール」を知るために役に立つ重要な指標なのです。
GDPの3つの測り方(生産・支出・分配)
実はGDPには3通りの視点から同じ数値を算出することができます。
これを「三面等価の原則」と言います(同じGDPを「生産面」「支出面」「分配面」で見ても結果が等しくなるという法則)。
まずは計算方法の概念を簡単に説明してから、下で共通の例を使って見てみましょう。
- 生産から計算: 国内で作られたすべての最終的な生産物の金額を合計します。モノやサービスがいくら生産されたかを計算し、それらをすべて足し合わせれば国全体で何円の生産をしたかがわかります。
- 支出から計算: 私たちが経済活動で使ったすべてのお金を合計します。国民がモノやサービスを買うために使った費用の合計で、個人の消費(食料品や生活品に使ったお金)、企業の投資(新しい工場や機械を買うための費用)、政府の支出(公共事業や教育・医療などに使ったお金)、そして貿易(輸出-輸入)をすべて合計します。
- 分配から計算: 企業や働く人が一年に得た所得をすべて合計する方法で、たとえばパン屋さんの収益(利益)やお店で働く人の給料、住宅を買われた人の土地代や家賃…そういう所得をすべて合計する方法です。ものを販売すれば利益が生まれ、人を雇えば給料が生まれる、それらを合計した金額がGDPと同じ数値になります。
例:実際に3つの方法で計算してみよう
下記の小さな経済を例に、生産・支出・分配の3種類でGDPを計算してみます。
- 例: パン屋だけがある小さな国
ある小さな国には1軒だけパン屋さんがあり、1年で合計1000円分のパンを生産して売りました。この国の人々はみんなパンが大好きで、1000円分のパンをすべて買い取りました。これを以下で計算します。- 生産面: 最終的な生産物「パン」の総額 = 1000円。小国のGDP = 1000円 (生産面)。支出面: 国民がパンを買うために使った費用 = 1000円。小国のGDP = 1000円 (支出面)。分配面: パン屋さんが1000円を売上げたとき、その内訳は給料 = 500円+利益 = 500円 (仮)でした。これらを合計するとやはり1000円になります。小国のGDP = 1000円 (分配面)。
これが「三面等価の原則」です。いろいろな見方から経済を見ても、結局生み出された価値は同じだよ!ということですね。
さらに他の例を見てみます。
ある小さな国に、農家さんが育てた米を100円でパン屋さんに売り、その米を使ってパンを作り300円で消費者に売るパン屋さんがいたとします。
最終的な製品はパンですが、パンの価格には中間製品である米の値段も含まれています。
この場合、パンの最終価格だけを合計するか(GDP = パンの価格300円)、または各段階で新たに付加された価値の合計をするか(GDP = 米での付加価値100円 + パンでの付加価値200円)、どちらでもGDPは300円になります。
名目GDPと実質GDPの違い
GDPには大きく分けて「名目値」と「実質値」の2種類があります。
かんたんに言うと、名目GDPは「現在の物価で計算したGDP」、実質GDPは「ある基準年の物価に調整したGDP」を指します。
もっとかみくだいて説明すると、名目とは「名前上の数字」で、物価の変動を考えないその時点の総額。
一方、実質とは「実際の価値」で、物価変動の影響を除いて出した数字を示します。同じものでも、10年前と今では1000円の価値が違うので、GDPを比較するために物価を調整した数字が実質GDPなのです。
たとえば、10円の餅を今年10個作って売り上げたらGDP = 100円ですが、来年も同じ数量10個を作って、餅の価格が12円に値上がりするとGDP = 120円になります。
あなたはこの変化を見て「GDPが20%増えた」と思うかもしれませんが、内訳は「生産量は0個増」「物価が20%上がっただけ」とも言えますよね。
このように、名目GDPはその時点でどれだけの資金が動いたかを表し、実質GDPは物価変動を取り除いたベースで生産量がどれだけ増えたかを表します。
ニュースなどでも「実質でxx%成長」という表現が使われ、これは高すぎる物価上昇と生産量の成長を区別して考えよう!という意図があります。
GDPと生活:私たちにどんな影響が?
GDPは国のスケールを表す重要な指標で、その動きは私たちの生活にも大きな影響を与えます。ここからは、GDPと私たちの生活や社会全体にどんな関係があるのか見ていきましょう。
- 給料とGDP: GDPの中でも大きな割合を占めるのが労働者の給与(給料)です。私たちが働いてもらう給料やボーナスは、GDPを分配面から見たときに含まれる所得です。つまり、GDPが成長して社会全体が豊かになれば、それだけ私たちが勤める会社の業績も良くなり、給料アップやボーナスにも期待できます。反対にGDPが縮小すれば、給料が減ったり昇給が止まったりといった影響もありえます。
- 税金とGDP: GDPが成長すると、政府の税収も増えます。私たちがお財布から払う消費税や所得税、そういった税金は会社や人々の収益から生み出されます。GDPが大きければそれだけ政府が収入を得られる可能性も高まり、学校や道路、医療など大切な活動への資金を増やしやすくなります。
- 物価とGDP: GDPが成長して人の消費が増えると、物価が上昇(インフレ)することがあります。GDPが増えること自体はいいことですが、物価があまりに高すぎると私たちの日常の費用の負担が大きくなってしまいます。そこで、物価がどれだけ影響したかを見るため、実質GDPという指標が使われます。
- 景気とGDP: GDPが増える状態では、企業の売上も上がり、雇用も増えていきます。社会全体が豊かになると、それに伴って給料も上がっていくことが多いでしょう。これは景気がいい状態で、私たちの生活もより豊かになります。一方、GDPが連続で減ると、企業は売上が出なくなり給料を下げたり人員を減らしたりするかもしれません。これが景気が悪い時の様子で、政府も経済を立て直すためにさまざまな政策を取ることがあります。
まとめ
GDPは一見難しい単語ですが、その意味や測り方は、日常のお金の動きを知っていれば意外と理解できると思いませんか?
今回はGDPの基礎的な概念から一歩踏み込んで、3つの計算方法や名目と実質の違いまで見てきました。最後には、GDPが私たちの生活とどういった関係があるかをお話ししました。
日々のニュースでGDPの増減を見かけたら、ぜひ今回の話を思い出して「どうやってGDPを測ってたっけ?」「GDPが上がるとどんな影響があるのかな」と考えてみてくださいね。
GDPを理解することは、国の経済のニュースをずっと近く感じることにつながりますよ。
現在の経済を測る“ものさし”とも言われるGDP、これからも注目してみましょう!
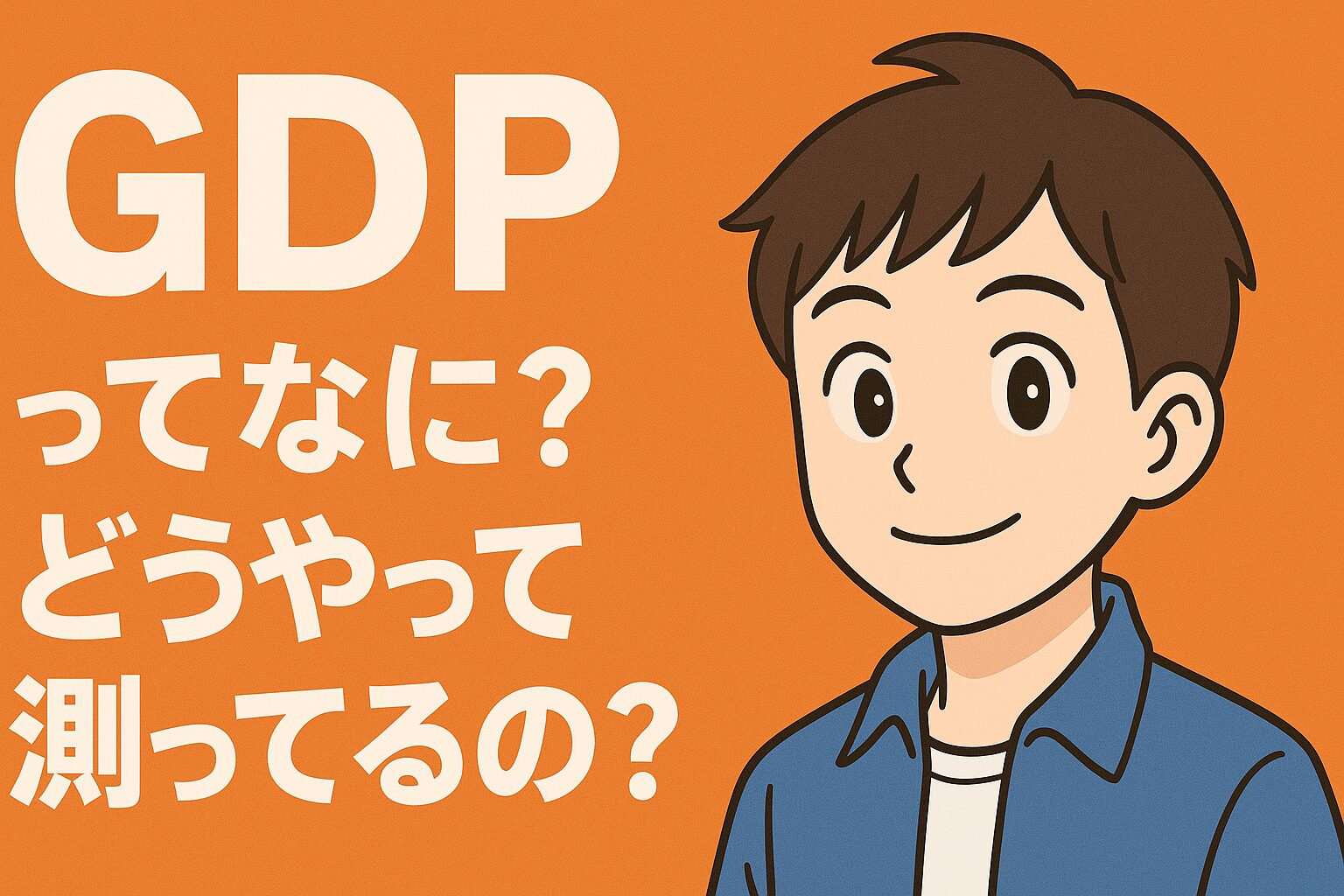
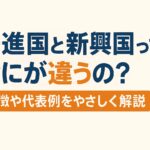

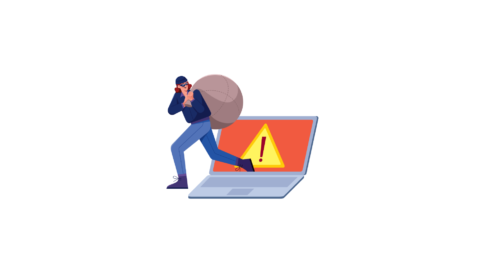
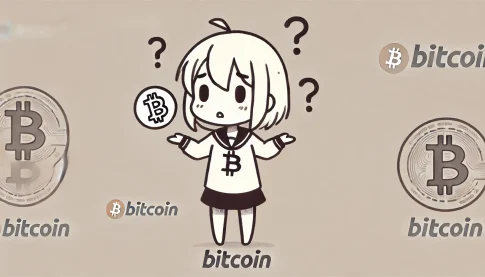

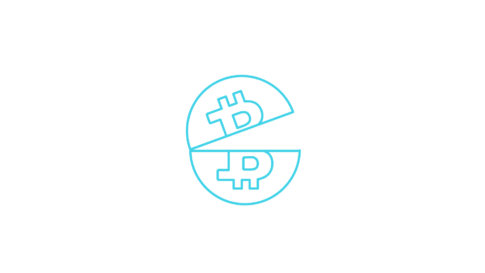





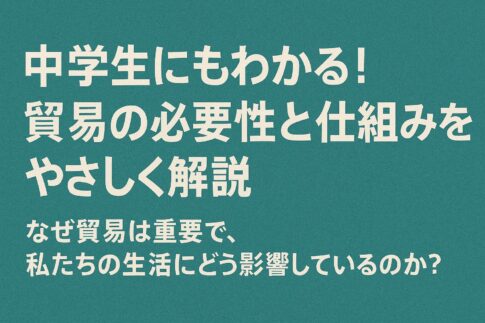
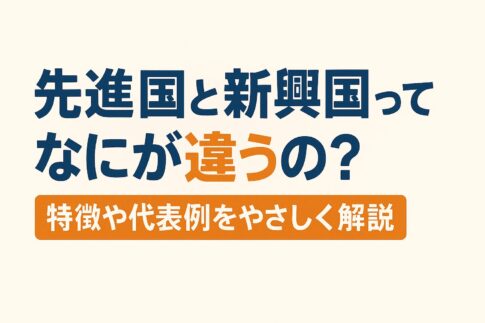




コメントを残す