S&P500(エスアンドピー500)とは、アメリカの代表的な株価指数で、米国の主要企業500社の株価をまとめたものです。
長い目で見ると、S&P500はこれまで上下しながらも全体的には成長してきました。
では、これから先の30年間もこの成長が続く可能性はあるのでしょうか?中学生にもわかるように、難しい言葉はかみ砕いて説明します。
考えるポイントは次の5つです
- 企業業績の動向(アメリカ企業の世界での競争力や今後のもうけの見通し)
- 金利の動向(金利を下げたり上げたりする可能性、アメリカの中央銀行の政策と市場への影響)
- AIなど技術の発展(ハイテク分野の成長が株価に与える長期的な影響)
- 地政学的リスク(米中関係や中東・ロシアなど国際情勢の緊張が与える影響)
- 政策の影響(トランプ大統領のような保護貿易や規制緩和の政策が株式市場に与える影響)
各項目について、将来のポジティブな要因(追い風)とリスク要因(向かい風)を整理し、最後にS&P500が長期的に成長し続けるかどうかの結論を考察します。
では、一つひとつ見ていきましょう。
企業業績の動向(米国企業の競争力と収益性)
企業の業績(もうけ)が伸び続ければ、株価も基本的には長期で上がりやすくなります。
特にS&P500に入っているような米国の大企業は、世界中でビジネスをして利益をあげています。その競争力と収益性が今後も高いまま保てるかが重要です。
米国市場の強さを示す図:世界の株式時価総額(株式の価値の合計)のうち、米国が占める割合はなんと50%以上にもなります。図中の雄牛(強気市場のシンボル)と文字が、2025年時点で*「米国が世界の株式価値の半分以上を持つ」*ことを強調しています。米国企業(特にハイテク企業)の巨大さがわかります。
ポジティブな要因: 米国企業はこれまで非常に強力で、世界中でビジネスのリーダーです。
実際、米国株式市場は世界全体の時価総額の半分以上を占めており、世界で最も価値のある企業トップ10のうち多くが米国企業です。
例えばApple社1社の価値だけでイギリスの株式市場全体に匹敵するほどで、Nvidia社もカナダとインドの市場を合わせたくらいの規模があります。
このようにアメリカ企業(特にテクノロジー企業)はグローバル競争力が非常に高く、世界中で製品やサービスを提供して大きな利益を上げています。
米国企業は効率よく利益を生み出す傾向があり、株主へのリターン(利益率)が歴史的に高めだとも言われます。
こうした強い企業の存在は、今後もS&P500の成長を支える追い風になるでしょう。
新興国が成長しても、米国企業はそこに進出したりテクノロジーで先行したりして利益を取り込む力があります。
また、新しい産業(例えば宇宙ビジネスやクリーンエネルギーなど)が生まれる際も、米国にはそれをリードする企業が出てきやすい土壌があります。
これらはS&P500にとって明るい材料です。
リスク要因
とはいえ、未来がずっと安泰とは限りません。
他国の企業との競争がさらに激しくなる可能性があります。例えば、中国やインドなどの企業が技術や規模で米国企業に追いつき、世界市場でシェアを奪うかもしれません。
また、米国企業の収益がこれ以上伸びにくくなる局面も考えられます。すでに現在、米国株式の株価はかなり高い水準にあります。
投資家たちは将来の大きな利益成長を見込んで株を買っていますが、もし期待ほど利益が伸びないと、株価が下がるリスクもあります。
実際、2024年初め時点でS&P500全体の株価収益率(PER)は約19.8倍と長期平均の15.6倍を大きく上回っており、高めの評価となっています。
これは「株価が割高」であることを意味し、企業の利益が高い成長を続けないと説明がつかない水準です。
さらに、米国企業は高い利益を上げていますが、人件費の上昇や原材料費の増加などコスト面の課題もあります。
利益率を維持するためにコスト削減や効率化が求められますが、それがうまくいかなければ利益成長が鈍る可能性があります。
また、将来的に環境規制や独占禁止法(巨大企業を解体するような動き)などで企業活動が制限されるリスクも否定できません。
こうした要因はS&P500の成長にブレーキをかける可能性があります。
金利動向(利下げ・利上げの可能性と市場への影響)
金利とはお金を借りるときの「利子」の割合で、経済においてとても重要な要素です。
アメリカの中央銀行であるFRB(連邦準備制度理事会)は景気や物価に応じて金利を上げ下げする政策をとります。
金利は株式市場にどんな影響を与えるでしょうか?
ポジティブな要因
一般に、金利が低い(お金が借りやすい)状況は株式市場にプラスに働きます。
企業は低い金利でお金を借りて工場を作ったり、新しい事業に投資したりしやすくなり、その結果利益が伸びやすくなるからです。
また、銀行預金や債券の利率が低ければ、投資家はより高いリターンを求めて株式にお金を向けやすくなります。
実際、2010年代の米国は金利が歴史的に低く、企業が安いコストで資金を調達できたため、大きな株価上昇の一因となりました。
今後30年という長いスパンで見れば、金利は景気に合わせて上がったり下がったりするでしょうが、米国の財政機関の予測では長期的な金利水準は過去30年の平均に近い水準に落ち着くとされています。
これは、金利が極端に高くなり続けたり、逆に超低金利がずっと続いたりはしないで、概ね「普通」の範囲に収まる可能性が高いという見方です。
仮にインフレ(物価上昇)が落ち着けば、FRBは景気刺激のために利下げ(政策金利を下げる)を行う余地もあります。
例えば2025年には、FRBは経済成長の減速を見越して年内に0.5%程度の利下げ(0.25%を2回)を行う見通しも示しています。
金利が下がれば企業や消費者に追い風となり、景気が良くなるので株式市場にとってプラスです。
まとめると、金利が適度に低い水準で安定して推移するなら、S&P500企業の業績拡大を助け、株価の長期的な上昇を支えるでしょう。
リスク要因
一方で、金利が上がることは株式市場に逆風です。FRBがインフレを抑えるために利上げ(政策金利を上げる)をすると、お金を借りるコストが上がります。
企業は資金調達が難しくなり、新しい投資を控えたりコスト削減を迫られたりします。
また、消費者もローン金利が上がると家や車を買いにくくなるため、企業の商品が売れづらくなり利益が減るかもしれません。
さらに、安全な国債や預金の金利が高くなると、わざわざリスクのある株式を買わなくてもいいやと考える投資家も増え、株式からお金が抜ける傾向があります。
例えば1970年代から1980年代初頭にかけて米国はインフレ退治のため金利を非常に高くした時期があり、その間経済は停滞し株式市場も低迷しました。
今後30年でも、もしインフレが再び暴走すればFRBは大幅な利上げを行うでしょうし、そうなれば一時的に景気後退(不況)が起きて株価が下がるリスクがあります。
また、長期的にはアメリカ政府の借金(国債発行残高)が増え続けており、その影響で国債金利が上がりやすくなる懸念もあります。
国債の利回りが上昇すれば企業もそれにつられて借入コストが上がるので、経済全体の重しになる可能性があります。
要するに、金利の急上昇や不安定な金利環境は企業業績と投資マインドにマイナスであり、S&P500の成長を妨げるリスクとなります。
AIなどテクノロジー分野の成長が株価に与える影響
次にテクノロジーの進歩についてです。
技術革新(イノベーション)は経済を成長させる大きな原動力です。
特に近年話題のAI(人工知能)をはじめとするハイテク分野の発展が、これから数十年の株式市場にどう効いてくるか考えてみましょう。
ポジティブな要因
新しい技術は経済の新陳代謝を促し、生産性を高めます。
たとえば過去を振り返ると、インターネットやスマートフォンの登場により世界中のビジネスの形が変わり、多くの企業が成長しました。
同じように、AIやロボティクス、新エネルギー技術などは今後の「産業の主役」になる可能性があります。
特にAI(人工知能)は、21世紀の「電気」や「蒸気機関」に匹敵するほど経済にインパクトを与えると言われています。
ある試算では、AI技術によって2030年までに世界全体で約15.7兆ドル(約1700兆円)もの経済効果が生まれる可能性があるとされています。
地域別に見ると、その恩恵は中国でGDPの+26%、北米(主に米国)でも+14.5%もの上乗せ効果になるという予測です。
これは非常に大きな数字で、AIによって新しい製品やサービスが生まれたり、人々の生活が便利になったりして経済規模自体が拡大することを意味します。
経済が大きくなれば企業の売上や利益も増えやすく、結果として株価にもプラスです。
実際、2023年には生成AI(チャットGPTのような技術)への期待が高まり、ハイテク株が株式市場を大きく牽引しました。
今後も、自動運転車や空飛ぶ車、バイオテクノロジーによる新薬開発、さらには今は想像もできないような技術革新が起こるでしょう。
アメリカはこうした最先端技術の開発で先頭を走る企業が多いので、技術の進歩=米国企業の成長につながりやすい土壌があります。
新しい技術は効率を上げコストを下げ、企業の利益率を押し上げてくれる追い風にもなります。
例えばAIを使って工場を自動化すれば人件費が削減できるかもしれませんし、AI解析で無駄を省けば利益が増えるかもしれません。
このように、技術分野の発展は長期的に見てS&P500全体の成長エンジンになり得るのです。
リスク要因
しかし、技術の発展には不確実性もあります。
まず、新技術のブームが来ても必ず勝者になれる企業ばかりではないという点です。
AIのポテンシャルは大きいものの、どの企業がその果実を手にするかは予測が難しいと指摘されています。
かつて1990年代後半のインターネット・バブル(ドットコムバブル)では、多くのIT企業の株価が急騰しましたが、2000年頃にバブルがはじけて多くの企業が倒産・株価暴落しました。
当時、生き残った本当に強い企業(AmazonやGoogleなど)はその後大成長しましたが、それ以外の多数の企業は淘汰されています。
この歴史が示すように、技術革新はハイリスクハイリターンです。
AIも同様に、一時的な過熱感から株価が先走りし、その後現実の普及が追いつかず失望されるというアップダウンが考えられます。
また、AIの導入が進むことで雇用の置き換えが起き、人々の仕事が奪われる不安もあります。
短期的にはAIで仕事を失う人が増えると消費が冷え込むリスクや、社会不安から規制が強まる可能性もあります。
さらにサイバーセキュリティ(AIを悪用した犯罪など)の新たなリスクも出てくるでしょう。
技術そのものの失敗もありえます。例えば新技術に巨額投資したものの期待した成果が出なければ、その企業の業績は悪化し株価も下がります。
総じて、技術革新は長期的な追い風である一方、熱狂と失望の波があること、そして新技術にうまく適応できない企業は置いていかれる可能性があることがリスク要因として挙げられます。
地政学的リスク(国際情勢の緊張と株式市場への影響)
地政学的リスクとは、国と国との関係悪化や戦争・紛争など、地理的・政治的な要因によるリスクのことです。
現在の世界を見渡すと、米中関係の緊張、ロシアとウクライナの戦争、中東情勢(例えばイランやイスラエル・パレスチナの問題)など様々な火種があります。
こうした国際情勢は、米国企業や株式市場に良くない影響を与える場合があります。
ポジティブな要因
地政学リスクというと悪いことばかりに思えますが、一つ覚えておきたいのは「大きなイベントがあっても、株式市場は意外と乗り越えて成長してきた」という歴史です。
例えば過去80年ほどのデータを分析したJPモルガンの研究によれば、戦争や国際危機などの地政学イベントがあっても、アメリカの大型株(S&P500のような大企業株)の長期的なリターンに持続的な悪影響はほとんど見られないという結果が出ています。
これは、短期的には株価が大きく下がる局面があっても、その後比較的早く回復してきたことを意味します。
現に、2022年にロシアがウクライナに侵攻した際、株式市場は一時不安定になりましたが、米国市場はその年の後半には落ち着きを取り戻しました。
なぜ大きな危機でも株式市場は持ちこたえるのか?
それは、企業が環境の変化に適応する力を持っているからです。
戦争や貿易摩擦があっても、企業は生産拠点を移したり仕入先を変えたりしてビジネスを続けますし、新しい需要も生まれます。
また、政府や中央銀行が不況を避けるための対策(景気刺激策)を行うことも多く、結果的に経済が極端に落ち込まないよう支えられます。
さらに、もし仮に世界のどこかで大きな問題が起きても、地域的な話にとどまる限り米国の大企業への影響は限定的になることもあります(例えば中東のある国で政変が起きても、影響はその国と関係の深い企業に限られるなど)。
平和で安定した国際環境が一番望ましいのは言うまでもありませんが、過去の実績を見ると、たとえ波風が立っても長い目では成長軌道に復帰している――これは株式投資において希望が持てるポイントです。
リスク要因
とはいえ、現在進行形の国際リスクはいくつもあり、それらが悪化すると経済・市場に相当な打撃を与える可能性があります。
まず米中関係の悪化です。米国と中国は世界最大の経済大国同士ですが、近年は貿易摩擦やハイテク分野での覇権争いなど「新冷戦」とも言われる状況にあります。
関係がこれ以上に悪化し、お互いに輸出入を大きく制限したり制裁の応酬になったりすれば、米国企業は大きな市場(中国)を失うリスクがあります。
またサプライチェーン(供給網)が分断され、部品や原材料の調達が困難になる恐れもあります。
実際、トランプ前大統領時代に米中間で関税の掛け合い(貿易戦争)が起きたときは、多くの企業がコスト増に直面しました。
この関税政策により、米国経済は成長が鈍りインフレ率が一時的に上昇したとFRB議長が指摘しています。
さらに極端なケースですが、台湾を巡って米中が軍事衝突する、といった事態になれば世界経済に深刻なダメージを与え、株式市場も大暴落する可能性があります。
次にロシアや中東の紛争です。
ロシアのウクライナ侵攻はヨーロッパのエネルギー供給を不安定にし、エネルギー価格の高騰を招きました。
同様に中東で戦火が広がれば原油価格が急騰し、世界的にインフレを加速させる恐れがあります。
インフレが進めば前述のように金利が上がり、経済にブレーキがかかります。
また不安な状況では企業も設備投資を控えます。
政治的な不透明感も株価の敵です。
たとえば選挙や政権交代によって外交方針が変わると、企業はそれに対応しなければなりません。
国際協調が損なわれ各国が保護主義(自国優先)に走ると、世界全体の経済成長率が下がる可能性があります。
以上のように、地政学リスクが現実化するとエネルギーや食料の価格高騰、サプライチェーン寸断、需要減退など複合的な悪影響が起きうるため、S&P500の成長も一時的にストップしたり、場合によっては後退(株価が大きく下がる)局面があり得ます。
政策の影響(保護主義・規制緩和など政府の方針と株式市場)
最後に政府の経済政策について考えます。
政府がどんな方針をとるかは、企業活動や市場に大きな影響を与えます。
ここでは具体例として、2017~2020年のトランプ大統領時代の政策を引き合いに、減税や規制緩和と保護主義(貿易制限など)の影響を見てみます。
ポジティブな要因
政府が企業に優しい政策をとれば、株式市場にとって追い風です。
例えば減税があります。企業が払う法人税を減らせば、その分企業の手元に利益が残り、株主に還元したり新規投資に回したりできます。
トランプ政権は2017年に大規模な税制改革を行い、法人税率を35%から21%へと引き下げました。
この法人税の大幅減税は米国企業の利益を押し上げ、結果として株価上昇に貢献したと評価されています。
当時、金融機関の分析では「税率引き下げによってS&P500企業の利益が向こう2年間で20%以上も増加するだろう」と予測する声もありました。
実際その後数年間、企業の一株当たり利益(EPS)は跳ね上がり、株式市場は力強い上昇を見せました。
また規制緩和(企業に課されているルールを緩めること)も株価にはプラスです。
トランプ政権は環境規制や金融規制の緩和を打ち出し、企業にとってビジネスしやすい環境を作ろうとしました。
例えば金融業界では規制を緩めることで銀行のもうけが増える可能性があり、それも企業収益にプラスに働くと期待されました。
さらに、インフラ投資や特定産業の振興策など、経済を活性化させる政府支出も株式市場には好材料です。
政府がお金を使って需要を生み出せば企業の売上が伸びます。
総じて、減税・規制緩和・産業振興策といったビジネスフレンドリーな政策は、企業利益を増やし株価を上げる要因となります。
リスク要因
逆に、政府の政策が企業活動の足かせになる場合もあります。典型例が保護主義的な政策です。
トランプ前大統領は「アメリカ・ファースト」を掲げ、外国との貿易に高い関税を課すなどの保護主義的政策を取りました。上述した米中貿易戦争がその一例です。
関税をかけると確かに国内産業は守られる面もありますが、同時に輸入原料の価格が上がったり報復関税で輸出が不利になったりして企業のコスト負担増や市場縮小を招きます。
実際、FRBのパウエル議長は「トランプ政権の大規模な輸入関税は、米国経済の成長を鈍らせインフレを押し上げた」と述べています。
インフレが上がれば前述のように金利上昇を引き起こし、景気にも悪影響です。
また、政府が特定の産業に介入しすぎると市場原理が歪み、企業が本来の競争力を発揮しにくくなることもあります。
もう一つのリスクは政治の不安定さです。
極端な政策の転換や政権の混乱(例えば政府の機能停止や予算審議の難航)などは、市場に不確実性をもたらします。
企業は先の見通しが立たないと積極的な投資ができず、市場もネガティブに反応します。
トランプ政権の時期、減税などポジティブ策もありましたが、Twitter発信による突然の政策表明など先行きの読みにくさが市場のボラティリティ(変動)を高めた面もありました。
さらに、将来また保護主義的な政権が誕生したり、あるいは逆に企業への課税強化や独占規制を厳しくする政権が出たりすれば、企業には逆風です。
このように政府の方針ひとつで、株式市場にはプラスにもマイナスにも作用し得るため、長期の成長を考える上で無視できない要因です。
結論:S&P500は長期的に成長を続ける
以上5つの観点から、S&P500の今後30年間の見通しをポジティブ要因とリスク要因の両面で整理してみました。
では、総合的に見てS&P500はこれからも成長し続けると考えられるでしょうか?
結論として私たちが考えるのは、「長期的には成長を続ける可能性が高いが、順風満帆とは限らない」ということです。
以下に理由をまとめます。
- 経済と企業の成長力
アメリカ経済は今後緩やかになるとはいえ拡大を続ける予測であり、それを牽引する米国企業の競争力も引き続き高い水準にあります。
世界の富の多くを生み出しているのが米国企業である事実、そしてAIなど新技術による新たな成長エンジンも控えている点から、大きな成長の土台はしっかりしています。
S&P500は時代とともに構成企業も入れ替わり、新陳代謝しながら成長していく仕組みなので、たとえ古い産業が衰退しても新しい産業が指数を押し上げる力になるでしょう。 - 過去の実績と長期のリターン
S&P500は過去数十年スケールで見ると年平均で7%前後の実質リターン(インフレを差し引いた成長率)を上げてきました。
仮に今後その半分の3~4%程度の実質成長にとどまったとしても、30年あれば元の規模の2倍以上にはなります(例えば年3%の実質成長でも30年で約2.4倍、インフレ分を加味した名目成長ならもっと大きくなります)。
つまり、多少スローペースでも複利の力で着実に資産は膨らむのです。
一時的な景気後退や暴落が途中で起きても、長期では乗り越えてきたのがこれまでの米国株式市場です。
この経験則は将来についてもある程度の安心材料になります。 - 潜在的なリスクへの備え
一方で、リスク要因も軽視はできません。
特に地政学リスクや政策の不確実性は、タイミングによっては大きなショックを与えるでしょう。
将来30年の間には、おそらく避けられない不況や金融危機的な局面もあるはずです。
その際にはS&P500が数年間低迷したり一時的に成長が止まる可能性も十分あります。
例えば2020年のコロナショックではS&P500も急落しましたが、巨額の経済対策と企業の順応力で短期間で回復しました。
将来も同様に、危機→政策対応→回復というサイクルを繰り返すと考えられます。
ただし、気を付けたいのは長期の平均回帰に過信しすぎないことです。
例えば2000年から直近までの約20年間は、ネットバブル崩壊と金融危機を経験した影響で、実質リターンは年3%程度と歴史的平均より低い結果でした。
したがって、今後30年も必ず高成長すると断言はできません。成長はするが前よりゆるやか、というシナリオも十分あり得ます。
以上を踏まえれば、S&P500は「人口増加の鈍化」「気候変動対策のコスト」「債務問題」など課題も抱えつつ、それでも世界経済の中心としての地位とイノベーションによる活力によって、長期では緩やかながらも右肩上がりの軌道を描く可能性が高いと言えるでしょう。
例えるなら、S&P500の成長は大きな木が年輪を重ねて太くなっていくイメージです。
雨風(不況や危機)にさらされる年もあるかもしれませんが、根(企業の実力)がしっかりしていて養分(技術革新や市場)がある限り、少しずつでも成長を続けるでしょう。
まとめとして、株式市場(S&P500)は短い期間では上がったり下がったりしますが、長い目で見ると経済の成長につれて大きくなる傾向があります。
ただ、その道のりは一直線ではなく、景気や金利、技術の発展や世界の出来事によって曲がりくねることもあります。
これから30年先、世界は今と違った姿になるでしょうが、もしアメリカ企業が引き続き世界をリードし、人々の生活を豊かにする商品やサービスを提供し続けるなら、S&P500も長期的には成長を続けている可能性が高いでしょう。
その成長の恩恵を受けるためには、アップダウンに一喜一憂せず、長いスパンで経済の行方を見守る視点が大切だということも付け加えておきます。







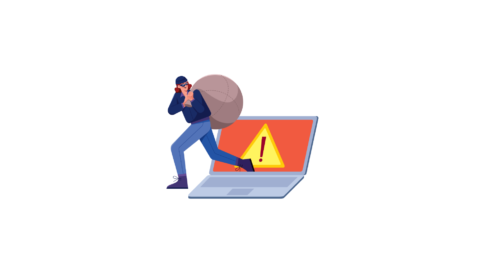

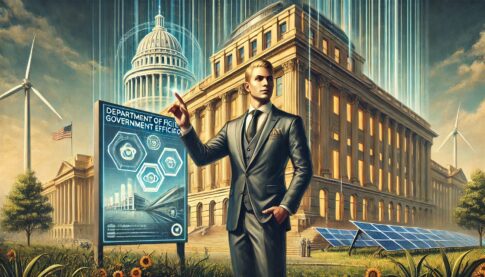




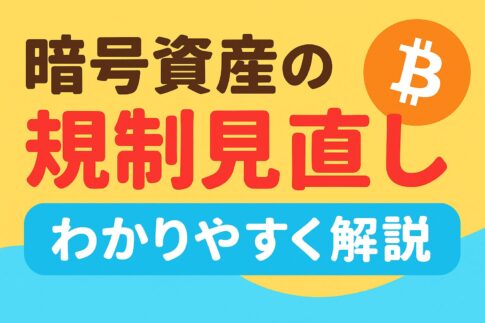




コメントを残す